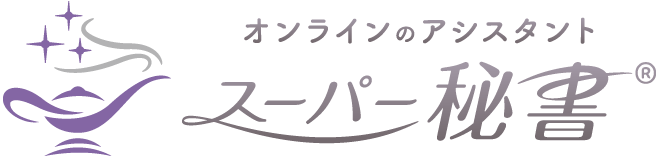2025年8月23日

2016年(平成28年)に地方創生を目的として創設された企業版ふるさと納税。
地方公共団体が行う地方創生の取組みに対して企業が寄付をすると、法人関係税から控除が受けられる制度です。
大きな節税効果を得ながら同時に地域にも貢献できるお得な制度として、注目を集めています。
ただ、スモールビジネス経営者にとっては注意が必要です。
最終的に税額控除として実質的な資金は戻ってくるものの、先に寄付をする必要があるため一時的にキャッシュフローが厳しくなることがあります。
また、本社が所在する地方自治体への寄付は対象外など、さまざまな制限があります。
この記事では、スモールビジネス経営者に向けて、企業版ふるさと納税の仕組みやメリット・デメリット、導入ステップを解説します。ぜひ参考にしてください。
企業版ふるさと納税の仕組みとは?

企業が地方自治体に寄付を行うことで最大9割の税控除を受けられる制度です。
対象となる寄付先は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトのみ。
一覧は内閣府の「企業版ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されています。
税控除を受けられるのは、法人税、法人住民税、法人事業税です。
寄付金に加え、専門的知識・ノウハウを持つ民間企業の人材を、寄付活用事業やプロジェクトに従事させる人材派遣型のふるさと納税もあります。
人材を派遣することで企業のノウハウをより積極的に活用できるため、意思疎通がしやすい、寄付の効果を実感しやすいといったメリットもあります。
同時に企業の人材育成の機会としても活用できます。
創設当初の2016年(平成28年)度には459社、118の自治体のみの利用で、寄付総額は7.5億円でした。
2020年(令和2年)度には1,640社、533団体が利用し、寄付総額は110億円を突破。
2021年(令和4年)度には4,663社、1,276団体にまで増え、寄付総額は341.1億円になりました。
2023年(令和5年)度には7,680社、1,462団体が利用。
寄付金総額は470億円にのぼるなど、既に多くの企業・自治体が活用しています。
企業版ふるさと納税は、2027年(令和9年)度まで実施されます。
今後、期限が延長されるかどうかは未定です。
企業版ふるさと納税の利用を検討しているなら、早めに動き出しましょう。
どのようなプロジェクトに活用される?
寄付を受け取った自治体は子育て支援、教育、人材育成、観光振興、環境対策、移住促進など、これまで予算不足で実施できなかった地域独自の課題に資金を活用します。
同時に自治体は民間企業の知見・ノウハウの活用ができるため、革新的なアイデアが得られる、事業の効率化が進むといったメリットもあります。多くの企業が悩みや課題をプロジェクトにして、企業からの寄付を受け付けています。
通常のふるさと納税との違い
個人でふるさと納税をしたことがある方も多いでしょう。
個人のふるさと納税では、寄付する自治体に制限はなく、個人の所得税・住民税から控除されます。
また、寄付金額に応じて地域の特産品などの返礼品が受け取れます。
返礼品を楽しみにふるさと納税をしている方もいるかもしれませんね。
一方、企業版のふるさと納税では、内閣府が認定したプロジェクトに10万円以上を寄付した場合のみ、税額控除の対象になります。 また、寄付の見返りに経済的利益を受け取ることが禁止されているため、返礼品はありません。
企業版ふるさと納税 税額控除の仕組み
通常の寄付では、損金算入によって寄付額の約3割の税負担が軽減されます。
企業版ふるさと納税では、寄付額の約6割が法人関係税から追加で税額控除されます。
つまり、最大で約9割の税負担が軽減されることになるため、企業の実質負担は1割で済むのです。
たとえば、1,000万円を寄付すると、最大約900万円の法人関係税が軽減できます。
詳しい仕組みは次の通りです。
まずは、寄付額の4割が法人住民税から控除されます。
法人住民税で4割に達しない場合は、その不足分を法人税から控除します。
また寄付額の2割は法人事業税から控除されます。
それぞれ上限があり、法人住民税、法人事業税は税額の20%、法人税は5%です。
中小企業が企業版ふるさと納税を使うメリットと注意点
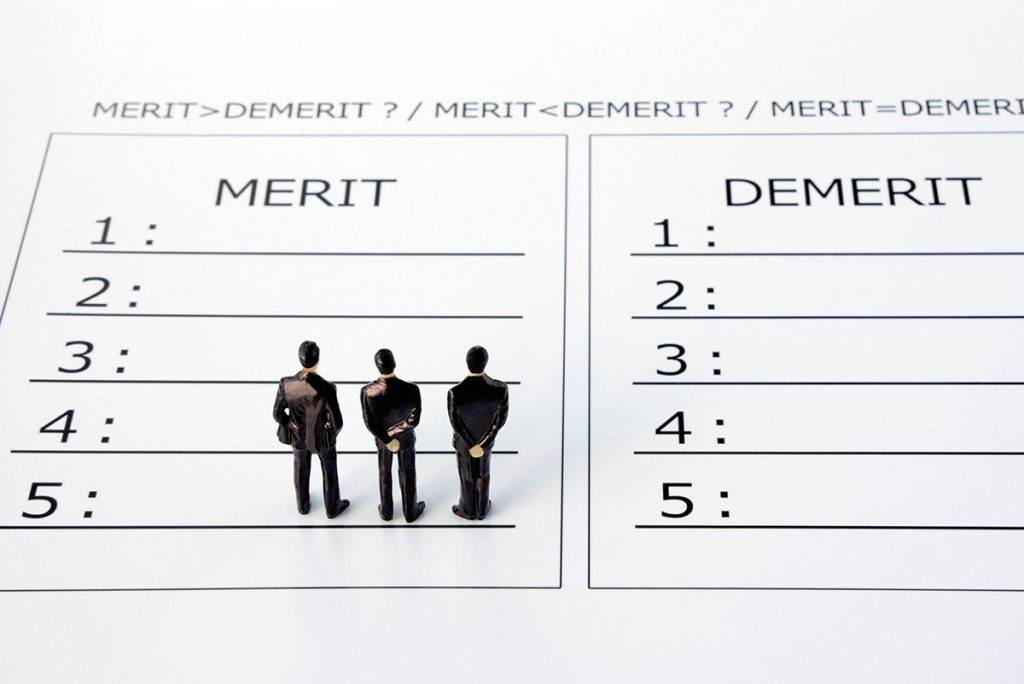
企業版ふるさと納税を使うことで、中小企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット① 実質的な節税が可能
もっとも大きいメリットは節税効果でしょう。
10万円以上の寄付をする必要があるものの、約9割の税額控除ができるため、10万円を寄付したら9万円分の税の軽減効果が得られます。
また、寄付金額の全額を損金として計上できるため、所得税の節税効果もあります。
法人税を納めている企業なら、企業規模を問わず企業版ふるさと納税を利用できます。
ただし、寄付による税の軽減効果が得られるのは決算後です。
一時的に寄付金額を支払う必要性があるので、資金繰りには気をつけましょう。
既に多くの法人関係税を支払っている企業ほど、節税効果は大きくなります。
一方、赤字企業や収益が少ない企業は、それほど節税効果はありません。
なぜなら、税額控除であるため、そもそも課税対象となる利益がないと税額控除ができないからです。
メリット② 地域貢献・ブランディングに活かせる
企業版ふるさと納税では、地域の産業・観光、人材育成、少子高齢化対策、定住・移住の促進など、さまざまな事業を支援できます。
寄付を行っても返礼品は受け取れませんが、地方公共団体のホームページや広報誌等に企業名が掲載される、施設に企業名が入った看板が設置されることが多いでしょう。
そのため、地域に貢献してくれる企業として地域住民からの好感度や認知度が上がり、ブランディングになります。
また、取引先や金融機関などからの信用力向上にもつながるでしょう。
地方公共団体と友好な関係を築ければ、企業と地域の双方にとってメリットのある新規事業を起こすなど、ビジネスチャンスも生まれます。
なお、寄付の見返りとして補助金を受け取る、有利な利率で貸付を受ける、寄付を公共事業の入札参加条件とするといったことはNGです。事業を受託する、新規事業を起こす際には、公正な手続きを心掛けましょう。
気候変動問題への関心が高まっていることをうけ、最近は地方自治体でも環境保全や脱炭素などのプロジェクトが増えてきました。
このような事業に寄付をすれば、自社だけでは難しいSDGs(持続可能な開発目標)達成へ貢献でき、企業のPRの一環となります。
社会貢献を重視する企業にとって、企業版ふるさと納税は節税効果とブランドイメージアップが一度に実現できるお得な制度です。
企業版ふるさと納税の注意点・デメリット
企業版ふるさと納税はお得な制度ですが、デメリットもあります。
まず、寄付できる自治体、プロジェクトが限られます。
国が認定していないプロジェクトに寄付をしても、9割の税額控除は受けられません。
また、地方交付税の不交付団体である都道府県・市区町村への寄付、本社が所在する地方自治体への寄付もできません。
寄付金の使途も地方創生に限定されます。
そのため、グローバルな社会課題へ対応したい、特定の科学技術研究を支援したいなどは叶いません。
地方創生以外の社会貢献活動をしたい企業にとっては、適していない制度といえるでしょう。
中小企業にとって苦しいのは、即効性に乏しいことです。
寄付をしたからといって、すぐに節税効果やブランドイメージが向上するわけではありません。
節税効果を得られるのは決算後であるため、一時的にキャッシュフローが厳しくなる可能性があります。
ブランドイメージの向上には時間がかかるうえ、寄付をしてもすぐにプロジェクトの結果がでるとは限りません。
寄付した自治体から優先的に事業を受注することは認められていないため、即効性を期待する経営者はメリットよりもコスト負担が大きいと感じるでしょう。
加えて、寄付には事務手続きの手間、コストも発生します。
具体的には、寄付先の自治体との事前協議、プレリリースの発行、税額控除の申請などです。事務手続きを行う手間と人件費を考えると、リソースの少ないスモールビジネス経営者にとっては負担が大きいものとなります。
企業版ふるさと納税の活用ステップ【中小企業向け】
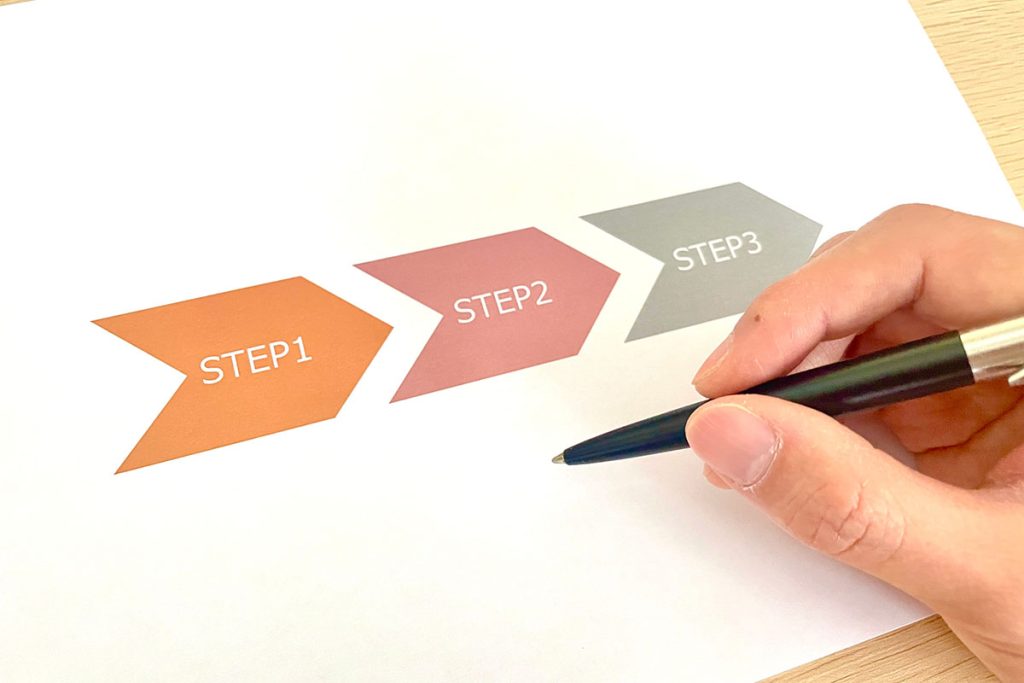
実際に企業版ふるさと納税を活用するためのステップを解説します。
ステップ① 支援したい自治体・事業を探す
ポータルサイトで支援したい自治体・事業を探しましょう。
企業版ふるさと納税ポータルサイト
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
特定の地域に寄付したい場合は「地域から探す」から都道府県を選択すると、自治体ごとのプロジェクト一覧が表示されます。その中から興味があるものを選びましょう。
本社がある自治体への寄付はできませんが、本社以外の事業所がある自治体なら寄付が可能です。
地域貢献を重視する場合は、本社以外の事業所がある自治体に寄付をするのもおすすめです。
サイトの一覧に載っていなくても、対象となるプロジェクトがあります。
もし、希望する自治体に寄付対象プロジェクトがない場合は、各自治体の担当部署に問い合わせてみてください。
寄付したい分野が決まっている場合は、「分野別の寄付募集事業一覧」を選択すると、起業支援、イノベーション、人材育成、移住、観光、環境保全など、25のジャンルからプロジェクトを選択できます。
また、定期的に企業と地方公共団体とのマッチング会が行われています。ZOOMによるオンライン開催で直接話を聞くことができるので、直接話を聞きたい場合はスケジュールをチェックしてみてください。
ステップ② 自治体と事前協議・寄付先を決定
寄付したいプロジェクトが決まったら、自治体に寄付の意向を伝えます。多くの自治体では、オンラインでの申し込みが可能です。
寄付前に、どの事業に対して寄付を行うか、寄付金額や時期を含めて自治体と調整します。寄付金は銀行振り込みが一般的ですが、自治体によって対応が異なるため、事前に確認しておきましょう。
ステップ③ 寄付の実施と証明書の取得
事前に自治体と取り決めた金額の寄付を行い、寄付金受領証を受け取ります。
これは税額控除を受けるために必要な書類なので、忘れずに受け取りましょう。
決算期をまたぐ場合など、地方公共団体の受領日や証明書の発行タイミングによっては、翌期の控除対象となるケースもあります。
受領書を受け取れる日時について、事前に寄付先へ確認しておくと安心です。
寄付による税額控除は、決算後の申告時に反映されます。
企業経営に支障が出ないよう、資金繰りを考慮して寄付額・寄付時期を決めましょう。
実際に活用した中小企業の事例紹介
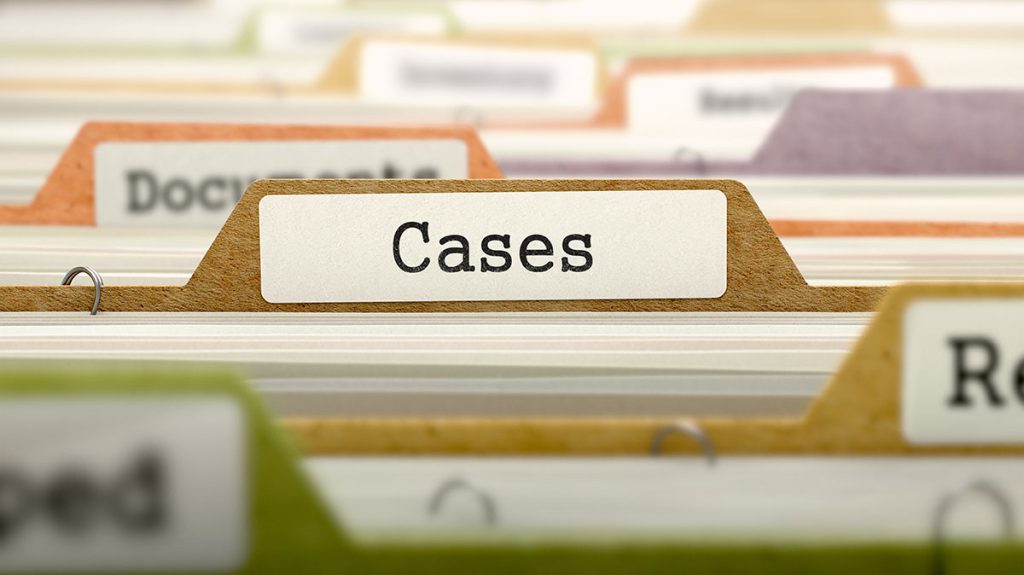
既に企業版ふるさと納税を利用した企業の事例を紹介します。
・リングロー株式会社
都内でIT機器リサイクル事業を展開しているリングロー株式会社。
⼭形県⾈形町のデジタルファースト推進事業に寄付を行い、廃校を再利用しながら、IT普及と地域活性化を目指す「おかえり集学校」プロジェクトを推進しています。
このプロジェクトでは、人材派遣型のふるさと納税を実施。
企業から人材を派遣し、町のデジタル活⽤⽀援員として自治体のデジタル化や町⺠のITリテラシーの向上に貢献しています。
廃校した学校を活用した「おかえり集学校」はITに関する相談や学習場所だけでなく、地域の人々が集える場所になるよう環境整備を行っています。
山形県舟形町「長沢集学校」、本格的な周知活動を開始▼
https://www.ringrow.co.jp/blog/2016/12/15/1692
・株式会社brinity
製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)や会計システムのコンサルティングを提供している株式会社brinityは、創立以来、サステナビリティを大切にして事業を行っています。
株式会社brinityは地域経済創生事業の拠点がある宮崎県延岡市の「延岡こども未来創造機構」プロジェクトに寄付を行い、子どもたちの「生きる力」を育む取り組みを支援しています。
ほかにも、延岡市のデジタル化の促進、脱炭素社会の実現のプロジェクトに対して寄付を行うなど、地域に貢献しています。
《宮崎県延岡市》企業版ふるさと納税を活用した寄附に関する感謝状贈呈式に出席▼
https://brinity.co.jp/press_37-2/
今こそ検討したい「企業版ふるさと納税」活用のすすめ

企業版ふるさと納税は、大きな節税効果を手にしながら、ブランドイメージ向上に貢献できるお得な制度です。
寄付金額は10万円以上~と、比較的少額から挑戦できるので、中小企業でも取り組みやすいでしょう。
自治体のプロジェクトに1社で寄付をすることもできますが、多くの場合、複数の企業が出せる範囲で資金を出し合ってプロジェクトを推進しています。
寄付金額が少なくても地方創生に貢献でき点も魅力といえます。
少しでも興味を持ったら、内閣府のポータルサイトで寄付先を検討してみてください。
数多くのプロジェクトが掲載されています。
企業版ふるさと納税は、2027年度(令和9年)まで実施されますが、その後も同じ条件で継続されるかは未定です。
少しでも興味があるなら、今すぐ動き出すことをおすすめします。
忙しくて寄付先を探す時間がない場合は、スーパー秘書にお任せください。
寄付したい事業、自治体など、希望をお知らせいただければ、寄付先をピックアップしておまとめします。