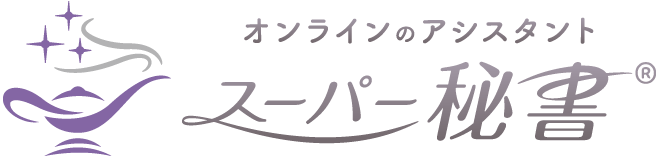2025年9月23日
2025年8月4日

「オンラインアシスタント」という言葉を聞いて、「難しそう」「どうやって使えばいいの?」と感じたことはありませんか?
実は、専門的な知識がなくても導入できる便利なサポートサービスなんです。
最近では、経営者や担当者の方が本業に集中するための手段として注目を集めています。
しかし、初めての方にとっては、どんな仕事を頼めるのか、どう依頼すればいいのか、信頼して任せられるのかといった不安があるのも事実です。
この記事では、オンラインアシスタントの基本的な仕組みや導入のコツ、よくある疑問や注意点などを、初めての方にもわかりやすく丁寧にご紹介していきます。
自分に合った活用法を見つけるためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
オンラインアシスタントとは?何ができる?どんな人に向いている?
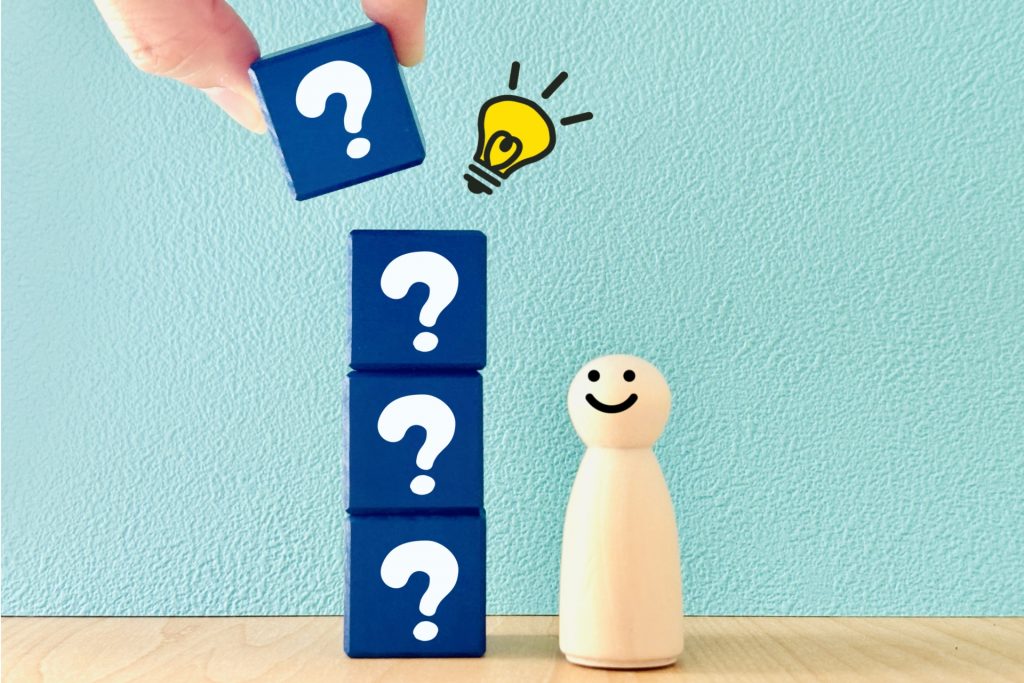
難しそうに聞こえるけど、どんな仕事をしてくれるの?
オンラインアシスタントとは、インターネットを通じて業務をサポートしてくれる外部スタッフのことです。
直接会わず、チャットやメール、クラウドツールを活用して、業務の一部を任せることができます。専門的なスキルが必要というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実際には一般的な事務作業や日常的な庶務も数多く依頼されています。
主な業務の例としては以下のようなものがあります。
- スケジュール管理:Googleカレンダーなどを使って予定を整理・共有
- メール対応:受信メールの整理や返信の下書き作成
- データ入力:ExcelやGoogleスプレッドシートへの情報入力
- 資料作成:プレゼン資料や営業資料の下書き作成
- 会議設定:ZoomやGoogle MeetなどのURL発行や出席者への案内
- 書類整理:PDF化やクラウド保管、ファイル名の統一など
- チャット対応:LINEやSlackでの社内外のやり取り補助
こうした作業は日々の業務の中で意外と時間を奪うものばかりです。
それらをオンライン上のアシスタントに任せることで、業務効率を大きく改善できる可能性があります。
オンラインアシスタントが活躍する場面とは
オンラインアシスタントが力を発揮する場面はさまざまです。
特に以下のような場面で役立ちます。
- 小規模企業や個人事業主が、総務や経理などの担当者を雇う余裕がないとき
- スタートアップなどで人手が足りず、事務業務に時間を割けないとき
- 一時的なプロジェクトで、数週間だけ補助的な作業が必要なとき
- 拠点が複数ある企業で、物理的な距離を超えてバックオフィス業務を統一したいとき
これらの場面では、業務の属人化を防ぎつつ、スムーズにタスクを進めることが求められます。
オンラインアシスタントは、リモートで対応可能な業務であれば、地域や時間帯を問わず依頼できるため、そうしたニーズにマッチしています。
また、オンラインでやり取りが完結することで、人件費やオフィススペースなどの固定コストを抑えながらも業務の質を保つことが可能です。
導入しているのはどんな企業?
オンラインアシスタントを導入しているのは、IT業界やベンチャー企業に限りません。
以下のような幅広い業種や組織が導入しています。
- 不動産業:物件情報の入力や問い合わせ対応など
- 士業(弁護士・税理士・行政書士など):顧客対応や書類作成補助
- 医療機関:予約管理や書類データ化
- 教育機関:講座申込者の対応や資料送付
- 通販・EC企業:受注データの整理や問い合わせ対応
- 地方自治体やNPO:事務作業や広報のサポート
導入している企業の多くは、「人手不足だけれどフルタイムの採用までは難しい」という事情を抱えています。
また、「ルーティン業務だけを効率化したい」「繁忙期だけサポートがほしい」といったケースも多く見られます。
このように、必要なときに、必要な分だけ業務を任せられるという点が大きな魅力といえます。
自分の業務でも頼めるのか見極めるには?
オンラインアシスタントに業務を依頼できるかどうかを判断するには、まず日々の業務の中で「自分でやらなくてもいい作業」が何かを見つけることがポイントです。
次のようなチェックポイントを参考にしてみてください。
- 毎日または毎週、繰り返し発生している事務作業がある
- 作業にかける時間の割に、利益や生産性が上がっていない
- 本来の業務に集中したいが、庶務や雑務に追われている
- 社内に事務専任のスタッフがいない、もしくはリソースが限られている
もしひとつでも当てはまる場合、その業務は外部に切り出せる可能性が高いです。
さらに、クラウドツールをすでに利用している、または導入予定がある場合はオンラインアシスタントとの相性が良く、スムーズに依頼しやすくなります。
クラウドツール例:
- Google Workspace(カレンダー、ドライブ、ドキュメントなど)
- Chatwork、Slack、LINEなどのチャットツール
- Zoom、Google Meetなどのオンライン会議ツール
- Dropbox、Notion、Trelloなどの情報共有・管理ツール
業務の棚卸しや洗い出しは、依頼内容を明確にするだけでなく、無駄な作業の削減にもつながります。
まずは、自分が「手放しても支障がない業務」をピックアップしてみるのがおすすめです。
導入前に知っておきたい!オンラインアシスタントのメリット

「本業に集中できる」って本当?
オンラインアシスタントを利用する最大のメリットのひとつは、本来の業務に集中しやすくなることです。
日々の中で発生するこまごまとした作業は、一つひとつは短時間でも、積み重なると大きな負担になります。
たとえば、毎日のメールチェックや請求書の作成、会議資料の更新、スケジュールの調整などが該当します。
これらの業務をアシスタントに任せることで、経営者や担当者はより重要な判断業務や顧客対応に時間を使えるようになります。
特にひとり社長や少人数で動いている会社では、業務が属人化しやすく、「やらなければいけないこと」に追われがちです。
オンラインアシスタントが業務を一部代行することで、余計な負担を減らし、頭の中を整理しやすくなります。
タスクの整理ができるようになることで、優先順位が明確になり、結果としてパフォーマンスも高まります。
社員を増やさずに仕事量を減らせる仕組み
新しく社員を採用するには、求人掲載から面接、教育、契約など多くの手間と時間がかかります。
その上、人件費や社会保険料なども発生します。オンラインアシスタントは、こうした固定コストをかけずに人手不足を補える手段として注目されています。
特に業務量に波がある企業では、必要なときだけ依頼できるという柔軟性が大きな魅力です。
たとえば、月末の請求書発行やイベント準備のように、特定のタイミングで業務が集中する会社にはぴったりです。
さらに、契約形態にも幅があり、時間単位での契約やスポット的な依頼も可能なため、定常的な採用よりもはるかに低リスクで始められます。
以下のような場面で、オンラインアシスタントの導入は特に有効です。
- 経理や請求処理を担当していた社員が退職してしまった
- 新しい業務が増えたが正社員の採用予算が出ない
- 一時的なプロジェクトで業務量が急増している
- 固定費を増やさずにサポート体制を整えたい
業務の質を維持しつつ、人件費を抑えるという点で、現代の働き方に合った選択肢と言えるでしょう。
業務内容に合わせて柔軟に依頼できる
オンラインアシスタントの魅力のひとつは、業務ごとに必要なスキルを持つ人に直接依頼できることです。
秘書業務、経理処理、SNS運用、Web更新など、分野に応じたスキルを持ったアシスタントが対応するため、必要な業務を、必要なタイミングで切り分けて依頼することができます。
依頼の自由度が高いため、以下のような使い方が可能です。
- スケジュール調整は秘書系アシスタントに、経理は会計経験者に依頼する
- 営業リスト作成だけを短期で頼む
- 月に10時間だけ稼働するプランを組む
また、クラウドツールの活用により、物理的に同じ場所にいなくてもスムーズに情報共有ができる環境が整っています。
たとえば、GoogleドライブやDropboxなどを通じてファイルをやり取りしたり、ChatworkやSlackでリアルタイムなコミュニケーションを取ったりすることができます。
秘書がいない経営者向けの活用方法は、「秘書がいない経営者必見!オンラインアシスタントの活用術」をご覧ください。
はじめてでも安心して使える理由とは?
オンラインアシスタントに対して「コミュニケーションが取りにくそう」「うまく指示が出せるか不安」という声も多く聞かれます。
ですが、実際にサービスを利用している企業の多くが、初回のやり取りから丁寧にフォローしてくれる体制を整えています。
特に、オンラインアシスタントサービスを提供する会社を通じて依頼する場合、以下のような点で安心感があります。
- 担当ディレクターが間に入り、ヒアリングから導入までサポートしてくれる
- 業務内容に合ったアシスタントを選定してくれる
- チャットツールの使い方ややり取りのルールも説明してくれる
また、初回は短時間の依頼からスタートし、相性や仕事の進め方が合うかを確かめることができるため、いきなりフル稼働で契約する必要はありません。
以下のようなサポートがある会社を選ぶと、はじめてでもスムーズに始めやすくなります。
- トライアルプランの提供がある
- 日本語での細やかな対応が可能
- 契約や依頼の仕方がわかりやすくまとめられている
- 担当者とのやり取りがテンプレート化されている
導入の初期段階では「どう伝えればいいか」に悩むこともありますが、やり取りを重ねることでお互いのスタイルが自然と固まっていきます。
最初からすべてを任せようとせず、少しずつ任せる範囲を広げていくことが、オンラインアシスタントをうまく使うコツです。
オンラインアシスタントに頼める仕事って?業務の種類をわかりやすく解説

メール返信・資料作成など日常的な業務
オンラインアシスタントに依頼できる業務の中でも、まず思い浮かぶのが日常的な事務作業です。
これらの業務は比較的依頼しやすく、はじめての方でも取り入れやすい内容です。
特に多いのが以下のような業務です。
- メール整理:重要なメールの抽出や未読チェック、返信の下書き
- 資料作成:PowerPointやGoogleスライドを使った企画資料の作成補助
- データ入力:ExcelやGoogleスプレッドシートへの顧客情報・売上データの入力
- 書類の整理・分類:フォルダ構成の整理、ファイル名統一、PDFへの変換など
こうした日常的な作業はひとつずつは短時間で終わるものでも、積み重なると業務の負担になります。
オンラインアシスタントはそれらをまとめて対応することができるため、時間の節約に直結しやすい業務領域といえます。
特にGoogle WorkspaceやDropboxなど、クラウドで共有できる環境が整っていれば、やり取りもスムーズです。
依頼側はファイルの場所を指定するだけで、アシスタントが整理してくれることもあります。
経理や人事などバックオフィス業務もOK
事務業務に加えて、オンラインアシスタントにはバックオフィス系の業務を依頼するケースも増えています。
これは、会社を運営するうえで欠かせないけれど、専門職を雇うにはコストがかかる分野です。
依頼が多いバックオフィス業務には、以下のようなものがあります。
- 請求書の発行:フォーマットの作成、取引先別の出力と送付
- 経費精算チェック:提出内容の確認、Excelへの取りまとめ
- 給与明細のデータ整理:勤怠情報のまとめ、給与情報の入力補助
- 人事関連の文書作成:求人票の原案、面接日程の調整
これらの業務は担当者の負担が大きくなりやすく、ミスが許されない作業が多い分野です。
そのため、事前に業務マニュアルやチェックリストを共有し、オンラインアシスタントと連携しながら作業を進めると、ユーザーエクスペリエンスの質が安定します。
クラウド会計ソフトや給与管理ツールなどを利用している場合、そのIDを共有することでアシスタントが作業を代行することも可能です。
ただし、個人情報や財務データを取り扱うため、事前に守秘義務契約を交わすことが大切です。
マーケティングやSNSのサポートも依頼可能
最近では、オンラインアシスタントの活用範囲が拡大し、SNS運用やマーケティング分野のサポートを依頼する企業も増えています。
これにより、社内の広報担当やWeb担当の負担を軽減できるようになります。
依頼可能な業務には次のようなものがあります。
- SNS投稿スケジュールの作成:曜日ごとの配信プランの調整と整理
- 投稿用画像の作成:Canvaなどのツールでテンプレートを使った画像作成
- コメント・DMの一次対応:質問対応やリアクションへの返信
- メルマガ原稿の下書き:配信内容の構成案作成や誤字脱字チェック
- キーワードの整理と入力:SEOを意識したロングテールキーワード選定など
これらの業務は、特にローカルビジネスやスモールビジネスにおいて、Web上の露出を高める手段として重要な役割を果たします。
SNSを活用してお客様との関係性を築きたいけれど、手が回らないという企業にとって、アシスタントの活用は大きなメリットとなります。
投稿画像作成やメルマガ作成では、ブランドイメージや言葉遣いのすり合わせが重要になるため、初回に具体的な事例や希望のトーンを伝えると安心です。
業務内容ごとに依頼の仕方も変わる?
オンラインアシスタントに依頼する際は、業務の種類によって、伝え方や準備する資料が異なります。
たとえば、メール整理やデータ入力のように明確なルールがある作業は、テンプレートやマニュアルを用意するだけでスムーズに進められます。
一方で、SNS運用や営業資料の作成のようにクリエイティブ要素がある作業は、完成イメージの共有や参考資料の提示が必要になることがあります。
業務ごとの依頼の工夫:
- 単純作業:マニュアル・チェックリスト・操作手順を共有しておく
- 定型業務:フォーマット化されたテンプレートを準備する
- 発想型業務:過去の資料や参考事例、イメージに近い投稿を伝える
- 外部と関わる業務:返信ルールやNGワードなどのルールを明記する
業務を依頼するうえで大切なのは、「どうやって伝えるか」よりも、「どこまで任せるか」を明確にすることです。
作業のゴールや納期をきちんと伝えれば、途中のプロセスはアシスタントに任せることができ、依頼側の負担も減らせます。
また、最初からすべてを任せる必要はありません。まずは「1日1時間分だけ」「週に1回の定型業務だけ」など、スモールスタートで始めると安心して進めやすくなります。
そうすることで、業務範囲を徐々に広げる判断もしやすくなります。
オンラインアシスタントで依頼できる仕事の詳細は、「オンラインアシスタントの業務内容とは?依頼できる仕事をわかりやすく解説」で確認できます。
オンラインアシスタント導入でよくある「不安」と「注意点」

指示がうまく伝わるか心配な方へ
オンラインアシスタントの導入で最も多い悩みのひとつが、「自分の意図がうまく伝わるか不安」というものです。
対面でのやり取りと違って、表情や声のトーンが見えにくいため、指示が曖昧になりやすいのも事実です。
こうした不安を減らすには、初回の依頼内容を丁寧にまとめて伝えることが大切です。
依頼時に意識したいのは、以下の3点です。
- 目的とゴールを明確に伝える
- 期限と優先度を必ず書く
- 使用してほしいフォーマットや参考資料を共有する
「うまく伝える自信がない」と思う場合は、最初に過去の資料ややってほしい業務のイメージを共有するだけでも十分です。
アシスタント側も不明点を確認しながら進めてくれるため、少しずつ意思疎通の精度は高まります。
外部の人に社内情報を任せて大丈夫?
オンラインアシスタントは企業の内部情報や業務内容を扱うため、「外部の人に社内の仕事を任せても大丈夫なのか」と不安に思う方は少なくありません。
実際には、多くのアシスタントサービスでは、以下のような対策をとって業務にあたっています。
- 業務委託契約書に機密保持条項を明記
- クラウド上での作業に限定し、ローカル保存を禁止
- 業務範囲を限定して情報の共有を最小限にとどめる
こうした体制が整っていることを確認するには、契約前に確認すべき書類や方針について質問しておくことが重要です。
また、社内で以下のようなルールを設けておくことで、さらに安心して業務を任せられます。
- 顧客リストや売上情報など、重要データのアクセス権を制限する
- 初回は業務の一部だけを任せて反応を見る
- 特定のツールやフォルダのみ使用を許可する
不安を完全にゼロにすることは難しいですが、仕組みとルールを整えることでトラブルのリスクは大きく減らせます。
セキュリティ・守秘義務の対応はどうなってる?
オンラインでのやり取りでは、セキュリティ対策がきちんと取られているかどうかも気になるポイントです。
情報漏洩や不正利用を防ぐために、企業側とアシスタント側の双方で意識すべき点があります。
オンラインアシスタントを利用する前に確認しておきたいチェック項目:
- 契約書に守秘義務や情報管理に関する項目があるか
- 使用するツールは暗号化やアクセス制限が可能か
- パスワード管理や共有の方法は明確にルール化されているか
オンラインアシスタントの多くは、社内教育や内部マニュアルに基づき、セキュリティ意識を高く持って対応しています。
中には、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの外部認証を取得しているサービスもあります。
業務内容に応じて、データの扱い方やアクセス制限をきちんと設計しておくことが、情報漏洩を防ぐ大きなカギになります。
不安を解消する「小さく始める」コツとは
初めてオンラインアシスタントを使うときにおすすめなのが、最初から多くの業務を任せるのではなく、限られた範囲で「試してみる」ことです。
不安を感じやすい依頼初心者の方には、以下のような進め方が向いています。
- 単発で完結する業務から始める(データ入力、会議日程の調整など)
- 時間制契約で1日1時間だけ試してみる
- スモールタスクで業務の質や対応スピードを確認する
こうした使い方をすると、アシスタントとの相性ややり取りのスタイルがわかるため、次に何を任せるか、どの業務なら安心して外注できるかが見えてきます。
小さく始めるときは、以下のような業務が取り入れやすくなります。
- メールの下書きチェック
- 簡単なデータ入力やリスト作成
- 資料の誤字脱字チェック
徐々にやり取りに慣れていけば、自然と依頼範囲を広げていくことができます。
「まずは少しだけ試してみる」ことで不安を取り除くことができます。
業務を丸投げせず、段階的に依頼を増やしていくことで、安心してオンラインアシスタントを活用できるようになります。
導入の流れと最初にやるべき準備とは?

トライアルや相談サービスを活用しよう
最近では、多くのオンラインアシスタントサービスが無料または低価格で利用できるトライアルや相談サポートを用意しています。
これらを活用することで、サービスの質や自社との相性を確認することができます。
活用したいトライアルの特徴:
- 初回1時間無料での業務体験
- 担当窓口とのヒアリング
- おすすめの依頼内容の提案
- 対応可能な業務範囲の確認
- 操作ツールの使い方サポート
トライアル中は、相手の反応速度や報告の丁寧さ、指示内容の理解度などをチェックポイントにすると判断しやすくなります。
また、導入前の相談サービスでは、以下のような内容をヒアリングしてもらえることが多いです。
- 自社の業務内容や抱えている課題
- 実際に頼めるかどうか不安な業務
- ツールの知識やITリテラシーの程度
- 外部とのやり取りにおけるルールや希望
相談だけでも依頼内容を整理できることがあるので、まだ具体的な業務が決まっていない場合でも一度話してみる価値は十分あります。
依頼の進め方を明確にしておくと安心
オンラインアシスタントとのやり取りでトラブルを避けるためには、業務の流れや指示の出し方をあらかじめ明確にしておくことが重要です。
これは、依頼する側・受ける側どちらにとっても安心材料になります。
スムーズな依頼につながる準備:
- 業務の目的と納期を明確にする
- 指示内容は短くても「曖昧にしない」
- 利用するツールの使い方を共有する
- 報告頻度や確認タイミングのルールを決める
- トラブル発生時の連絡手段を設定しておく
一度運用ルールが整えば、以後のやり取りはより効率的になります。
最初から完璧でなくても大丈夫です。
実際に進めながら、調整・改善していけば問題ありません。
まとめ
オンラインアシスタントは、インターネットを通じて仕事を手伝ってくれる頼もしい存在です。
特別な準備や難しい技術がなくても、基本的なパソコン操作とやり取りができれば誰でも利用を始められます。
スケジュール管理やデータ入力、SNSの投稿準備など、日々の細かい作業を任せることで自分の大事な仕事に集中しやすくなります。
はじめは何を頼めばいいか迷うかもしれませんが、まずは「面倒だけど毎日やっていること」を整理することからスタートすると、依頼しやすくなります。
いきなり全部を任せる必要はなく、小さな作業から少しずつ始めることでやり取りにも自然と慣れていきます。
はじめてで不安な方も、担当者のサポートを受けながら少しずつ進めることができます。
仕事を効率よく進めたい、雑務から手を離したいと感じている方にとって、オンラインアシスタントは心強い味方になります。
現在、スーパー秘書では「1ヵ月1.98万円のおためしプラン」をご用意しています。
少しの作業から始めたい方、まずは試してみたい方にぴったりの内容です。
導入を迷っている方は、この機会にお気軽にお問い合わせください。