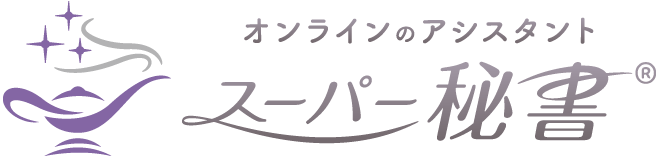2025年9月23日
2025年7月7日

近年、AIの進化とともに、オンラインアシスタントの活用が注目を集めています。
特に、業務の効率化や時間の有効活用を目指す企業や経営者の方々にとって、強い味方となる存在です。
ただ、実際にAIを導入したり、オンラインアシスタントに仕事を依頼したりする際には、どんな業務を任せられるのか、どこまで対応してくれるのかが気になる方も多いのではないでしょうか。
さらに、AIを使いこなすには意外と事前の準備や調整が必要になることもあります。
この記事では、AIとオンラインアシスタントの得意分野や役割の違いをわかりやすくご紹介し、うまく使い分けるためのポイントをお伝えしていきます。
実際の活用事例や運用の流れも交えて解説しますので、ぜひ参考になさってください。
AIが得意な業務とは?単純作業やデータ活用に強みを発揮

AI(人工知能)は、あらかじめルールやパターンが決まっている業務において非常に高いパフォーマンスを発揮します。
特に、時間がかかる単純作業や、正確性が求められる数値処理のような場面では、人間よりもはるかにスピーディーかつ安定したアウトプットが可能です。
ここでは、AIが得意とする代表的な業務と、企業でどのように活用されているかについて具体的に解説していきます。
くり返しの作業はAIがスピーディーに処理
AIは、同じルールでくり返す処理に強く、大量のデータ入力やファイルの分類、メールの仕分けなどを人の手を借りずに自動で行うことができます。
たとえば、アンケートの回答を自動で集計し、指定のフォーマットに整えるような処理は、AIにとって非常に得意な分野です。
また、毎日・毎週決まった時間に行うルーティン業務は、AIの導入で大きく効率化できます。
具体的には以下のような作業が該当します。
- 定型フォーマットへのデータ入力:顧客情報や売上などを入力する作業
- 書類の自動分類:請求書や領収書などを種類別に振り分ける
- リマインダー送信:社内の締切通知や定期報告メールの自動送信
人間が集中力を必要とする単純作業をAIに任せることで、作業ミスが減り、対応スピードも大幅に向上します。
数字に強いAIはデータ集計や分析にも最適
数値の扱いにおいて、AIは非常に正確で早く、売上データやアクセスログの分析などに活用されています。
たとえば、ECサイトであれば「どの商品が、どの時間帯に、どんな地域の人によく売れているか」といった細かい傾向を自動で分析することができます。
このようなデータは、マーケティングや在庫管理などにも活かされます。
AIが分析した結果をもとに、どの広告を出すか、どの商品を補充すべきかといったデータドリブンな判断が可能になります。
さらに、AIは数字を扱うだけでなく、そこから意味のあるパターンや傾向を導き出す力があります。
過去のデータと照らし合わせて、次に何が起こりそうかを予測する「予測分析」も、AIの得意分野のひとつです。
チャットボットでよくある質問に自動対応
お問い合わせ対応の現場でも、AIは広く使われています。
特に「よくある質問」に対する自動応答は、チャットボットの導入で対応コストを大きく削減できる例のひとつです。
たとえば、以下のような質問に対して、AIがリアルタイムで回答を提示することができます。
- 商品の納期についての問い合わせ
- サービスの料金プランの確認
- 登録手続きの流れの案内
これにより、担当者が対応に追われることなく、本来の業務に集中しやすくなるメリットがあります。
また、24時間体制での対応も可能になるため、ユーザーエクスペリエンスの向上にもつながります。
ただし、すべての問い合わせにAIが対応できるわけではありません。
複雑な相談や、柔軟な対応が求められる内容は、人の手によるフォローが不可欠です。
資料や文章の「たたき台」も自動で生成できる
近年では、AIが文章を生成する機能も進化しています。
たとえば、会議の議事録の下書きや、社内報の原稿、商品紹介の説明文など、「とりあえずの形」を作る作業にAIを活用するケースが増えています。
文章のたたき台があることで、ゼロから考える必要がなくなり、作業のスピードが格段にアップします。
また、同じような文言を何度も書く必要がある業務では、AIの生成機能が非常に重宝されます。
代表的なツールとしては、ChatGPTやNotion AI、Google ドキュメントのAI補助などがあり、用途に応じて選ぶことができます。
もちろん、生成された内容には「誤字脱字」や「事実と異なる記述」が含まれることもあります。
そのため、最終的な調整や確認は必ず人の目で行う必要があります。
AIに任せやすい業務の共通点とは?
AIが得意とする業務には、いくつかの共通点があります。
これを押さえることで、「どの業務をAIに任せればよいか」が判断しやすくなります。
- 手順が決まっている:同じルールで何度もくり返される業務
- 大量処理が必要:人がやるには時間がかかりすぎる業務
- 数字や文字に強い:定量的な情報を扱う場面
- 判断が単純:Yes/Noの判断が中心で複雑な配慮がいらない業務
このような条件に当てはまる業務であれば、AIを導入することで時間やコストを大幅に削減できます。
ただし、すべてをAIに任せればよいわけではありません。
AIと人、それぞれの得意分野を見極め、役割分担をうまく行うことが業務効率化のカギとなります。
実は大変?AIを使う前に必要な準備と調整作業のリアル
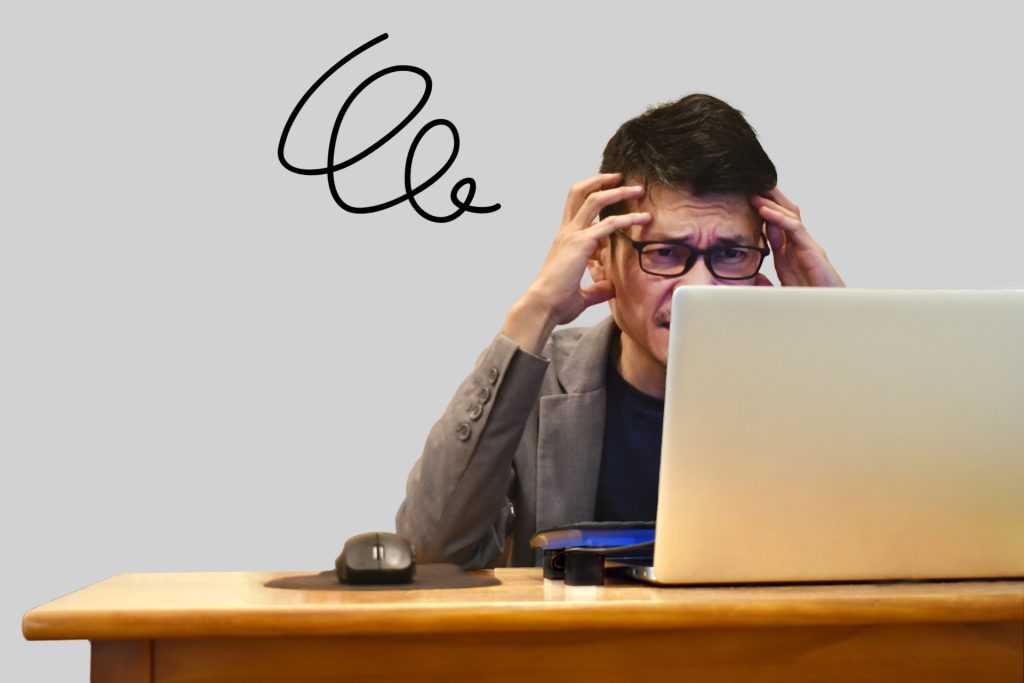
AIを業務に取り入れると、作業が自動化されて効率が上がるイメージがありますが、導入前に必要な準備や調整には意外と時間と労力がかかることがあります。
特に、AIに「何を」「どのように」頼むかを決める段階があいまいだと、思ったような結果が得られないこともあります。このような事前準備をスムーズに進めるために、オンラインアシスタントのサポートが役立つ場面も多くあります。
AIには「何を」「どう頼むか」を決める必要がある
AIに仕事を任せる場合、まず明確にする必要があるのが「どんな作業を」「どんなルールで」「どんな成果物として出力してほしいのか」という指示の内容です。
人に対する指示のように「雰囲気で伝える」ことができないため、かなり細かい情報まで明文化する必要があります。
たとえば、資料作成をAIに依頼する場合でも、次のような点を具体的に決める必要があります。
- 使用するデータや情報の範囲:どの資料をもとにするのか
- 出力形式の指定:PDF、スライド、テキストなど
- 文体やトーン:丁寧語にするのか、カジュアルでいいのか
- 対象読者の設定:社内向けなのか、外部向けなのか
これらを最初に決めずに依頼してしまうと、出力された内容が思ったものと大きく異なることも珍しくありません。
データの整理や入力が思ったより手間
AIが機能を発揮するためには、正確で整ったデータが必要になります。
しかし、実際にはそのデータを用意する段階で手間取ることが多くあります。
社内にある情報が複数のファイルに分かれていたり、更新されていない古いデータが混在していたりすることもあります。
AIは曖昧な情報や重複したデータに弱いため、事前に情報を整理・分類しておく必要があります。
これには時間がかかるだけでなく、誰がどの情報を持っているかを確認する作業も含まれます。
- 複数フォーマットの情報を統一:スプレッドシート、メモ、PDFなどの形式の整理
- 不要なデータの除去:重複や誤情報を取り除く作業
- ラベルやタグ付けの整備:AIが情報を分類しやすくするための調整
このような準備を怠ると、AIが誤った判断をしたり、余計な作業が発生するリスクが高まります。
指示があいまいだとAIの精度も下がる
AIは、あいまいな指示に対しては的確なアウトプットを返すことができません。
「それっぽいもの」は出せても、使えるレベルかどうかは別問題です。
たとえば「かっこいいデザインにしてほしい」「シンプルでわかりやすく」などの感覚的な言葉は、AIにとっては意味が広すぎます。
人なら会話の流れや表情から意図を汲み取れますが、AIは明確な基準がなければ判断ができません。
そのため、下記のような点を明確に言語化することが求められます。
- 何を「かっこいい」と感じるのかの基準を説明
- 使ってほしい色やレイアウトの指定
- 具体的な参考資料の提示
このように、AIに的確な成果を出してもらうには、かなり細かい指示が必要になることが多いのです。
最初の準備に時間がかかりすぎることも
AIは作業スピードこそ速いですが、それを最大限活かすためには事前の準備にかなりの時間を割く必要があります。
特に初めてAIを導入する場面では、何をどう頼めばよいかが手探り状態になることも多く、最初の依頼準備に思っていた以上の時間がかかるケースがあります。
その結果、「せっかく導入したのに活用できていない」という状態になってしまうこともあります。
AIの活用には、準備も業務の一部として見積もっておく必要があります。
- 業務フローの見直し:どこをAIに任せ、どこを人が担うのか整理
- 既存ツールとの連携確認:AIが連携できる環境を整える必要あり
- 社内での役割分担:AIへの入力担当やチェック担当を明確に
こうした背景を理解せずに導入すると、逆に負担が増えてしまうこともあります。
オンラインアシスタントが準備段階をサポートする事例
AI活用に必要な準備や調整は、オンラインアシスタントにとって得意な分野のひとつです。
たとえば、次のような業務でアシスタントが活躍しています。
- 指示内容の整理:社内メンバーの意図をヒアリングし、AI用に整理・整形
- データの集約と加工:社内の資料を集めて形式を統一したうえで整備
- 出力された成果物のチェック:AIの生成結果に不備や違和感がないか人の目で確認
オンラインアシスタントは、人の意図をくみ取り、AIが理解しやすい形で情報を整えることができます。
また、成果物がAIの想定通りでなかった場合に、再調整や再依頼の作業もスムーズに行えます。
こうした支援を受けることで、AI活用のハードルが下がり、業務の効率化がより現実的なものになります。
AI単体ではなく、アシスタントとの連携によって、初期導入の「つまずき」を回避することが可能になります。
オンラインアシスタントに頼める一般的な業務については、「オンラインアシスタントの業務内容とは?依頼できる仕事をわかりやすく解説」をご覧ください。
AIが生成した文章や資料を仕上げるのはアシスタントの大切な役目

AIによる文章生成や資料作成は、非常にスピーディーで便利な機能ですが、そのままでは使いにくい場面も少なくありません。
特に、言い回しの不自然さや、細かい情報のニュアンス、文脈への配慮などが欠けていることが多く、そのまま社外へ提出する資料やメール文として使うのはリスクを伴います。
そこで大きな役割を果たすのが、オンラインアシスタントです。
AIが作った“下書き”を整え、読みやすく、伝わりやすく仕上げるのは、人間の感覚や配慮に基づいた手作業の力です。
内容の確認・言い回しの調整は人の手で行う
AIが作成した文章は、あくまでたたき台であり、最終的な確認と調整が不可欠です。
とくに、言葉の選び方やトーンは、読み手の立場や状況に合わせて細かく整える必要があります。
オンラインアシスタントは、こうした文体の微調整や表現の確認において重要な役割を果たします。
特定の企業でよく使われる言い回しや、読者に応じた配慮のある表現など、AIでは判断が難しい部分を人の目と手で補うことができます。
- 丁寧語・敬語の調整:社外向け文書では敬語の使い分けが重要
- 目的に合ったトーンの調整:営業資料では説得力、社内資料ではわかりやすさを重視
- 読みやすい構成への修正:段落の切り方や見出しの付け方も整える
こうした作業により、読み手にとってわかりやすく、誤解のない文章が完成します。
情報の最新性や企業カラーへの対応もアシスタントが
AIが出力する情報は、最新であるとは限らないことに注意が必要です。
AIは過去の学習データや、設定された知識の範囲でしか情報を出せません。
そのため、企業ごとの最新情報や、新しい制度、最近の動向などが反映されていない場合があります。
また、企業ごとに文章のトーンや表現方針が異なるため「その会社らしい」文書に仕上げるためには、人による確認と調整が欠かせません。
オンラインアシスタントは、過去の資料やガイドラインをもとに、企業カラーに合った表現に整えることができます。
- 最新の情報への書き換え:納期や価格などの数値を最新のものに修正
- 企業独自の言い回しの採用:「お客様」→「ご利用者様」などの用語ルールに沿った表現調整
- デザイン・構成面での統一:フォントや色味、ロゴの配置など、企業のテンプレートへの落とし込み
AIによる作業がスピーディーであっても、人の手で細部を整えることで資料や文章の信頼性が高まります。
AIと人の役割分担で「精度の高い成果物」を実現
AIとオンラインアシスタントは、お互いの得意分野を補完し合う関係にあります。
AIが高速で作業のベースを作り、アシスタントが人の目線で確認・調整することで、精度の高い成果物が完成します。
- AIの役割:高速で下書きを生成し、定型作業を担う
- アシスタントの役割:内容のチェック、言葉の調整、全体の整合性を確認
このように、人とAIのバランスを取ることで、業務の効率化と品質維持の両立が可能になります。
すべてをAIに任せるのではなく、人の力を組み合わせてこそ、本当に使えるアウトプットが生まれます。
オンラインアシスタントの役割は、AIが生み出した「素材」を、実務で使える形に仕上げる大切な存在です。
オンラインアシスタントを活用する具体的なアイデアは、「秘書がいない経営者必見!オンラインアシスタントの活用術」で詳しく解説しています。
まとめ
AIは、文章の作成やデータの処理などを短時間で行える便利な仕組みですが、その力を十分に発揮するためには、事前の準備や出力された内容の調整が必要になることが多くあります。
特に、何をどう頼めばいいかを整理したり、AIが出した文章をそのまま使える形に整えたりするには、人の手によるサポートが欠かせません。
そこで頼りになるのが、オンラインアシスタントの存在です。
オンラインアシスタントは、AIに依頼するための準備を代わりに行ったり、AIの出力結果を見やすく整えて実務で使える状態にしてくれたりします。
また、社内の人がAIに慣れていない場合でも、使い方の説明やフォローを通して導入をスムーズに進めることができます。
AIを単独で使おうとすると意外なところでつまずくこともありますが、オンラインアシスタントを利用すれば、AIの力を無理なく業務に取り入れることができます。
AIをうまく使いこなしたいと考えている方にとって、オンラインアシスタントのサポートはとても心強い味方です。