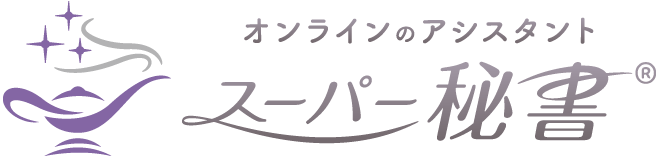2025年9月23日
2025年8月6日

日々の業務に追われて、「本業に集中する時間が足りない…」と感じたことはありませんか?
そんなときに頼りになるのが、オンラインアシスタントです。
オンラインアシスタントとは、インターネットを通じて業務を手伝ってくれる秘書のような存在で、事務作業やスケジュール管理、資料作成などをリモートでサポートしてくれます。
特に、一人で事業を運営している個人事業主や、少人数で会社を回している方にとって心強い味方になります。
この記事では、オンラインアシスタントについて初心者の方にもわかりやすく、どんなことが頼めるのか、どんな人に向いているのかなどを丁寧にご紹介していきます。
オンラインアシスタントとはどんなサービス?

オンラインアシスタントとは、インターネットを活用してさまざまな業務を遠隔でサポートしてくれるスタッフのことを指します。
通常のオフィスに常駐する秘書とは異なり、パソコンやスマホを通じてやり取りを行うスタイルです。
そのため場所を問わず業務を依頼できる柔軟さがあり、個人事業主や少人数の事業者にとって非常に心強い存在です。
自宅やオフィス外から業務をサポートしてくれる人
オンラインアシスタントの大きな特徴は、リモートで稼働することです。
つまり、アシスタントは同じオフィスにいなくてもメールやチャットなどを使って指示を受け、作業を行ってくれます。
例えば、東京都にオフィスを構える事業者が、北海道在住のオンラインアシスタントに業務を依頼することもできます。
地理的な制限がなく、全国から優秀な人材に業務を依頼できる点が大きなメリットです。
また、在宅勤務で対応できるため子育てや介護と両立して働いているアシスタントも多く、時間や条件に応じて柔軟に業務を引き受けてくれるケースが多いのも特徴です。
電話やメール、チャットでやり取りできる仕組み
オンラインアシスタントとのやり取りは、以下のようなツールを使って行われます。
- メール:業務内容の共有や報告に使われる定番の手段です
- チャット:Slack、Chatwork、LINE WORKSなど、即時の連絡や相談に便利です
- オンライン通話:ZoomやGoogle Meetを使った打ち合わせや進捗確認にも対応できます
- クラウドストレージ:GoogleドライブやDropboxなどでファイルの受け渡しを行います
- タスク管理ツール:TrelloやNotionなどで業務の進捗を共有することもあります
このように、対面ではなくてもスムーズに業務を進めるための手段が豊富にあるため、実際の働き方としても十分に機能します。
雇用ではなく契約で依頼する新しい働き方
オンラインアシスタントは、企業に直接雇用されるのではなく、業務委託契約などを通じて業務を遂行するスタイルが一般的です。
そのため、採用や人事評価といった手続きが不要で、短期間・小規模からでも気軽に依頼できます。
この働き方の特徴として、以下の点が挙げられます。
- 社員と比べて固定費がかからない:業務を依頼した分だけの費用で済みます
- 必要なタイミングで必要な業務を依頼できる:業務量に応じて稼働時間を調整できます
- トライアル的に始めやすい:月10時間などの少量プランも用意されていることが多いです
このように、人材を雇用するほどではないけれど業務を手伝ってほしいというニーズにぴったりなサービスといえます。
対応してもらえる業務の一例
オンラインアシスタントに依頼できる業務は、非常に幅広いです。
特に多く利用されているのは、以下のような事務やバックオフィス業務です。
- スケジュール管理:会議や面談の調整、カレンダー登録
- メール対応:お客様への返信や問い合わせの整理
- 書類作成:請求書や見積書などの作成と送付
- データ入力:顧客情報の整理、表計算の作成など
- SNS運用:投稿スケジュールの管理、コンテンツの下書きなど
- 経理サポート:領収書の整理、月次集計の準備
- ウェブサイトの更新:文章の修正、画像の差し替えなど
- マーケティング支援:リサーチ、メルマガの下書きなど
業務の範囲は契約内容やアシスタントのスキルによって異なりますが、一般的な事務作業はほぼ対応可能と考えて差し支えありません。
自分でやるには時間がかかる作業や、誰かに任せたいけれど人手が足りない…という時に、必要な部分だけ柔軟に任せることができるのがオンラインアシスタントの大きな魅力です。
利用を検討している場合は、まず自分がどの業務を手放したいのかを整理しておくことがポイントになります。
そうすることで、よりスムーズに導入しやすくなります。
オンラインアシスタントに頼める仕事をもっと知りたい方は、「オンラインアシスタントの業務内容とは?依頼できる仕事をわかりやすく解説」をご覧ください。
こんな悩みを抱える個人事業主におすすめ

雑務が多く本業に集中できない
日々の業務には、本来の専門業務以外に発生する雑務が数多くあります。
例えば、顧客とのメール対応、請求書の発行、会議日程の調整、SNS投稿のスケジューリングなど、すべてを一人でこなすには限界があります。
こうした業務が積み重なると、肝心の企画や戦略の立案、商品の改善やサービス品質の維持といった重要な業務に手が回らなくなってしまいます。
オンラインアシスタントに定型的なタスクを任せることで、思考力や判断力が求められる本業に集中する時間がしっかり確保できるようになります。
次のような業務を委託することで、業務負荷の分散が可能です。
- 書類の体裁チェック:見積書・請求書・契約書などのフォーマット整理
- カレンダー管理:商談や会議のスケジューリング、リマインド設定
- データ整理:売上データの整理、顧客リストの管理など
- SNSの下書きや投稿:定期更新の準備作業を代行
作業時間の削減だけでなく、ユーザーエクスペリエンスの改善にもつながる業務を効率的に進めることができます。
社員を雇うほどの予算がない
フルタイムの事務スタッフを社員やパートとして雇用する場合、給与のほかに保険料や備品費用などが発生し、毎月の固定費が大きくなりがちです。
特に立ち上げ間もない事業や小規模な事務所の場合には、人件費の負担は慎重に考える必要があります。
オンラインアシスタントは、次のような料金体系で利用できることが多く、コスト面でも柔軟です。
- 月10時間〜利用可能なプラン:必要な時間だけ依頼できる
- 定額+時間単価制:業務量に応じた料金設定が可能
- スポット依頼型:突発的な業務に対応する短期契約ができる
このように最小限の予算で業務を委託できるため、従業員を採用せずに業務効率を上げたい方に適しています。
料金相場は依頼する業務の専門性や対応時間帯によって異なりますが、一般的には月額2〜5万円程度から始められることが多いです。
費用面に不安がある方でも、まずはトライアル的に利用して無理のない範囲からスタートできるのも特徴のひとつです。
短時間・柔軟なサポートをお願いしたい
オンラインアシスタントのもう一つの魅力は、時間の自由度が高いことです。
たとえば、毎日3時間だけお願いしたい、繁忙期だけ依頼したい、午前中だけ対応してほしいといった要望にも柔軟に応じてくれる場合があります。
- 週単位・月単位で稼働時間を選べる:急な予定にも調整しやすい
- 業務ごとの依頼が可能:1件単位の作業で契約できることもある
- 複数のアシスタントで分担:1人でなく複数の得意分野を組み合わせることもできる
このように、業務の波やライフスタイルに合わせて無駄なく人材を活用できるのがオンラインアシスタントの強みです。
事前に「どの業務を、どれくらいの頻度で、どの時間帯に依頼したいか」を整理しておくことで、よりスムーズに希望通りのサポート体制を整えることができます。
オンラインアシスタントの具体的な活用アイデアは、「秘書がいない経営者必見!オンラインアシスタントの活用術」も参考になります。
人に仕事を任せることに不安がある
「自分でやった方が早い」「他人に任せるとミスが起きそう」など、仕事を手放すことに抵抗を感じる方も少なくありません。
ですが、そのまま全てを抱え込んでしまうと、いつか業務が回らなくなる可能性があります。
オンラインアシスタントは、業務の可視化と整理を促す役割も担ってくれます。
業務を依頼するには、作業内容を明確に言語化する必要があるため、自分の業務全体を見直す良い機会になります。
また、次のような工夫で不安を軽減することもできます。
- 業務マニュアルを作成して共有する:作業手順が標準化され、品質が安定しやすくなります
- チェックリストを使う:ミスを防ぐ仕組みを事前に用意することで安心して任せられます
- 定期的なフィードバックを行う:コミュニケーションの質が向上し、信頼関係が深まります
最初は一部の簡単な業務から任せてみるのが安心です。
オンラインアシスタントで対応できる主な業務

オンラインアシスタントは、個人事業主や小規模経営者が抱えがちな日常業務を幅広くサポートしてくれます。
実際にどのような業務を依頼できるのかを具体的に知ることで、自分の業務の中からどれを任せられるかを整理しやすくなります。
業務範囲は多岐にわたりますが、ここでは特に依頼が多い主要な業務についてわかりやすくご紹介します。
スケジュール調整やメール対応
日々の業務の中でも、スケジュール管理やメール対応に多くの時間を取られているという方は少なくありません。
こうした業務をオンラインアシスタントに任せることで、重要な商談やミーティングの準備に専念しやすくなります。
主に依頼されている作業内容には、以下のようなものがあります。
- カレンダーの更新や共有:GoogleカレンダーやOutlookを使って予定の追加や変更を行います
- アポイント調整:取引先やお客様との日程調整をメールやチャットで代行
- リマインド通知の設定:会議や締切の事前リマインドを自動化ツールと連携して行います
- 受信メールの仕分け:重要度に応じてラベル付けや返信の優先順位を整理
特にメール対応は、件数が多くなると読むだけでも負担になります。
返信文のテンプレートを作っておくことで、アシスタントが内容に合わせて適切な返答をしてくれることもあります。
資料作成やデータ入力などの事務作業
データをまとめたり資料を整えたりする事務作業は、時間がかかる一方で正確さも求められる業務です。
こうした作業をアウトソーシングすることで、空いた時間をコア業務に使えるようになります。
オンラインアシスタントによる事務作業の一例を挙げると、次のようなものがあります。
- 見積書や請求書の作成:テンプレートに沿って内容を入力し、PDF化まで対応
- 表やグラフの作成:売上推移や在庫管理データをExcelやスプレッドシートで整形
- 名刺データの入力:営業で獲得した名刺情報を顧客管理ツールに登録
- リサーチ業務:競合調査や市場データの収集とまとめを行う
こうした業務はルールを明確にしておけば、高い精度で再現性のある作業としてアシスタントに引き継ぎやすいのが特徴です。
経理・請求書まわりのサポート
日々の経理業務はルールやフォーマットが多く、慣れていないと時間も労力もかかります。
オンラインアシスタントはこうした業務の一部を負担してくれるため、作業ミスの軽減や経理効率の向上が期待できます。
対応可能な経理関連業務には次のようなものがあります。
- 請求書や領収書の整理:クラウド会計ソフトにアップロードしたデータの確認
- 入金状況のチェック:顧客ごとの支払い状況を管理リストに反映
- 経費の入力・集計:レシートや領収書をもとに日々の経費を分類
- 会計ソフトへの入力補助:freeeやマネーフォワードなどにデータを反映
なお、税務や年末調整のような専門的判断を伴う業務は税理士の領域になりますが、その前段階のデータ整理までならアシスタントでも十分対応できます。
SNSやwebサイトの更新・投稿管理
情報発信やブランディングに欠かせないSNSやwebサイトの運用も、日々の業務では後回しになりがちです。
オンラインアシスタントを活用すれば、更新作業の負担を減らし、発信の継続性を保つことができます。
よく依頼されている内容には以下のようなものがあります。
- SNSの投稿スケジュール作成:週単位や月単位で投稿内容と日時をまとめる
- 画像や文章の下書き:キャンペーン情報や商品紹介記事の原案作成
- ハッシュタグや投稿内容のチェック:ビッグキーワードやロングテールキーワードの見直し
- webページの修正依頼:文言変更やリンク更新などをCMSに反映
特にInstagramやX(旧Twitter)などでは、継続的な更新がユーザーエクスペリエンスに直結するため、投稿を習慣化できる体制づくりが重要です。
外部とのやり取りや発信のように個人事業主が後回しにしがちな分野こそ、オンラインアシスタントによるサポートが大きな助けになります。
依頼内容を具体化し段階的に任せることで、運用の効率化と品質維持の両立が目指せます。
利用の流れと準備しておきたいこと

オンラインアシスタントを初めて利用する方にとっては、どのように依頼を始めればよいのか、何を準備すればスムーズに進められるのかがわかりにくいこともあります。
事前に準備をしておくことで、依頼時のやり取りがスムーズになりミスや誤解も防げます。
ここでは、初回相談から実際の依頼までの流れと用意しておきたい情報について詳しくご説明します。
まずは相談や問い合わせから始めよう
オンラインアシスタントサービスを利用する最初のステップは、問い合わせや相談です。
ほとんどのサービスでは無料の相談やヒアリングを行っているため、いきなり契約せずに不安や疑問を解消することができます。
初回相談では、次のような内容を確認するケースが多いです。
- どんな業務を任せたいか
- 1日・1週間あたりの業務量や頻度
- 希望する対応時間帯(平日・土日・早朝・夜間など)
- 必要なスキル(Excelが使える、経理経験があるなど)
- 情報の取り扱いやセキュリティに関する希望
オンラインでの面談が設定される場合もありますが、チャットやメールでのやり取りだけで進められるケースも少なくありません。
事前に希望や条件をメモしておくと、相談がスムーズに進みます。
ヒアリングで自分の課題が明確になることもあり、アシスタントに任せるべき業務の優先順位を整理するきっかけにもなります。
契約前に伝えるべき業務内容とは?
アシスタントに業務を任せる前には、どのような作業をお願いしたいのかを明確に伝えることが重要です。
業務内容が曖昧なままだと、ミスや認識のズレにつながってしまいます。
依頼前に伝えるべき内容には次のような項目があります。
- 業務の目的:何を達成したいのか、どこまでを担当してもらうのか
- 作業の頻度とタイミング:毎日対応してもらいたいのか、週に数回でよいのか
- 使用するフォーマットや資料:請求書のテンプレートや表のデザインなど
- 参考になる過去のやり取り:前回のメールや作成済みの資料などがあると説明が簡単になります
曖昧な指示を避けるためにも、業務内容は箇条書きで整理し、ファイル共有ツールなどを使って明示的に共有するのがおすすめです。
業務フローが複雑な場合は、簡単な業務マニュアルを作っておくと相手も理解しやすくなります。
よく使われるツールや連絡手段
オンラインアシスタントとのやり取りは、すべてリモートで完結します。
業務内容やチームのスタイルに合わせて、使いやすいツールを選んでおくことが重要です。
よく使われている主なツールは以下のとおりです。
- メール:業務報告や日次・週次の共有に便利
- チャットツール(Slack、Chatworkなど):リアルタイムの連絡や相談に向いています
- ビデオ会議(Zoom、Google Meetなど):初回面談や業務引き継ぎ時に使用されます
- クラウドストレージ(Googleドライブ、Dropboxなど):資料やデータの受け渡しが可能です
- タスク管理ツール(Trello、Notionなど):進捗状況の確認や業務の分担に便利です
事前にどのツールを使うのかを決めておくことで、やり取りの効率が大きく変わります。
自社の業務に合わせて必要最低限のツールを選び、共有ルールを簡単に決めておくのがおすすめです。
業務引き継ぎ時のポイント
実際に業務を依頼する段階では、アシスタントに対して「何を」「どうやって」行うのかを伝える引き継ぎが発生します。
この引き継ぎの精度が高いほど、対応品質も安定しやすくなります。
引き継ぎをスムーズに行うために、以下の点に注意してみてください。
- 作業の手順を文書で渡す:業務マニュアルやToDoリストなどを事前に用意すると理解が深まりやすくなります
- 操作画面を録画する:ツールや作業内容を画面録画した動画で共有すれば、何度でも見返せて便利です
- 過去の作業データを共有する:これまでの資料やフォーマットを渡すことで、作業の仕上がりイメージが伝わります
- 定期的に確認時間を設ける:最初の1〜2週間は毎週進捗や疑問点を確認する時間を取るとズレを防げます
手間がかかるように感じるかもしれませんが、最初の準備をしっかりすることで長期的に見て大きな時短と業務効率化につながります。
ツールの操作に不安がある場合は、アシスタントに聞いてみるのもおすすめです。
多くの場合、複数のツールに慣れているスタッフが対応してくれるので、相談しながら進めることができます。
自分にとっても使いやすい仕組みを作っていく感覚で、柔軟にやり取りを重ねていくことが大切です。
まとめ
オンラインアシスタントは、毎日の業務に追われがちな個人事業主や小規模経営の方にとって、心強いパートナーになってくれる存在です。
資料作成やスケジュール調整、メール対応、SNSの更新など時間がかかる作業を代わりに対応してくれるため、本業に集中しやすくなります。
また、アシスタントを正社員として雇うよりも費用を抑えやすく、短時間だけ頼みたい方や、柔軟な働き方を求める方にも向いています。
依頼する際は、業務の内容や希望する対応時間を事前に整理しておくと、スムーズにやり取りが進みます。
いきなり難しい作業を任せるのではなく、まずは簡単な作業からお願いすることで、お互いの信頼関係を築いていくことが大切です。
連絡はチャットやメールで行うことが多く、資料のやり取りにはGoogleドライブやDropboxなどのサービスを使います。
わからないツールがあっても、アシスタントがサポートしてくれることが多いので安心です。
スーパー秘書では専属窓口のコーディネーターが親身に対応させて頂きます。
事務作業から経理、WEBサイトの更新、画像制作、動画編集、情報発信まで幅広く対応し、業務整理の段階からサポートしてくれる体制が整っています。
初めての方でも安心して始められるお試しプラン(1.98万円・最大1ヵ月)も用意されています。
「業務を手放したいけど何からお願いすればよいかわからない」という方も、まずは無料相談で気軽にご相談いただけます。
本業に集中できる働き方を、ぜひこの機会に見直してみませんか?