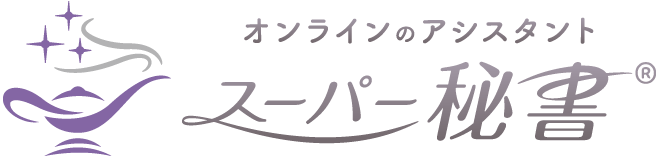2025年10月1日

ビジネスを拡大したい、事業投資や設備投資をしたい時に大きな助けとなる補助金。
しかし、補助金の申請手続きは複雑で、申請条件や交付条件は頻繁に見直しが入るため、1人で手続きを行うのは負担が大きいと感じているスモールビジネス経営者も多いでしょう。
中小企業診断士に経営相談から補助金の申請サポートまで、一括して依頼している経営者も多いかもしれません。
しかし、行政書士法の改正により2026年1月1日以降、中小企業診断士は補助金申請書類の作成・提出ができなくなります。
補助金の申請をしたいスモールビジネス経営者は、今後は誰に頼めばいいのでしょうか。
この記事では、頼れる専門家は誰なのか、中小企業診断士とのお付き合いはどう変わるのか、詳しく解説します。
補助金申請をめぐる最新動向をチェック

まず、補助金の最新動向をチェックしておきましょう。
中小企業の成長を促進するため、経済産業省、中小企業庁、厚生労働省、地方自治体など、国や自治体が補助金制度を用意しています。
補助金を利用できる業種の拡大、個人事業主を含む中小企業向けの制度の増加、手続きのオンライン化など、年々使い勝手が良くなっており、2025年には「中小企業新事業進出補助金」「中小企業成長加速化補助金」の2つが新設されました。
ここでは、数ある補助金の中でも、スモールビジネス経営者におすすめの補助金を紹介します。
・ものづくり補助金
経済産業省が行っている生産性の向上に取り組む事業者に向けた補助金です。
国内の新製品・新サービスの開発投資を支援する「製品・サービス高付加価値化枠」と海外事業の展開にともなう設備・システム投資を支援する「グローバル枠」の2種類があります。
補助上限額はプランによって異なります。
「製品・サービス高付加価値化枠」は従業員数によって750万円~2,500万円、「グローバル枠」は3,000万円が上限額です。
どちらの枠でも中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3の補助率が適用されます。
「製品・サービス高付加価値化枠」は、新製品・新サービスの開発を伴う事業に対して適用され、単に機械装置・システム等を導入するだけでは対象となりません。
他の補助金との併願が可能ですが、交付決定前に1つを選ぶ必要があります。
また、交付には補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%以上増加させることなどの条件があります。
結果が伴わない場合は、補助金を受け取れません。
・小規模事業者持続化補助金
中小企業庁が行っている小規模事業者の経営改善や販路開拓などの取組みを支援する補助金です。
チラシ作成や広告掲載、店舗改装など、幅広い販路開拓の経費が対象となるのが特徴です。
たとえば、新たな販路への商談に活用するため、洗練されたパッケージデザインやリーフレットを作成する費用にも補助金を利用できます。
一般型のほか、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型があります。
一般型・通常枠の補助上限は50万円、補助率は2/3と比較的少額の補助金ですが、申請手続きが簡素化されているため、手軽に利用できる点が魅力です。
申請には地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必要で、地域活性化や雇用創出に繋がる事業計画が評価されます。
中小企業診断士がこれまで担ってきた補助金申請サポートの役割
補助金申請には、応募申請書だけでなく、事業計画書、経費明細書など、さまざまな書類が必要です。
中小企業診断士は「経営戦略・事業計画」を専門領域としており、経営全体を客観的に見渡せる立場から、補助金申請のサポートをしてきました。
特に補助金申請に必要な「事業計画書」「経営改善計画」「資金繰り計画」など、事業戦略部分の策定支援は中小企業診断士の強みです。
市場分析、競合調査、財務分析を踏まえた根拠ある計画づくり、補助金の審査ポイントに沿ったストーリー構築などができるため、採択率の高い申請書類の作成が可能です。
実績報告や支払証憑の整理など、補助事業終了後の経営効果検証までトータルでサポートしてもらえることが多いため、中小企業診断士に頼る企業が多いのです。
また、多くの場合、中小企業診断士は「認定経営革新等支援機関」に所属しています。
認定経営革新等支援機関とは、一定レベル以上の専門性を持っていると国の認定を受けた支援機関です。
補助金申請の際、支援機関のサポートを受けることを推奨しているケースもあるなど、支援機関に頼ることで採択されやすい、不備のない申請書ができあがります。
行政書士は書類作成・申請、税理士は税務の分野に関しての専門家であり、経営について詳しいとは限りません。
つまり、支援機関に所属している中小企業診断士に申請サポートを依頼すれば、補助金の採択率、交付率が高まるといえます。
2026年からの行政書士法改正とその影響を解説

申請書類の作成、提出、効果検証まで中小企業診断士に任せていた企業が多い中、行政書士法が改正されました。
これにより2026年以降、中小企業診断士が申請業務を行うと法律違反になります。
違反行為があった際には、違反をした行為者だけでなく、依頼した法人も責任が問われます。
知らなかったでは済まされないため、しっかりと改正について把握しておきましょう。
今回の法改正では、次の4つの点が変更されました。
1.行政書士の使命規定の追加
今まで、行政書士の使命は明確に規定されていませんでした。
今回の改正では、弁護士法・税理士法・司法書士法などと同様に、行政書士法の第1条に使命が規定されました。
2.職責の追加
行政書士が守るべき基本姿勢が追記されました。
また、マイナポータルとの連携のほか、電子申請やオンライン審査の拡大など、デジタル化が進んでいることを受け、デジタル時代に求められる役割が明文化されました。
3.業務の拡大
これまで不服申立て手続きの代理を行えるのは、自らが作成した書類だけでしたが、今回の改正により、本人が関与していない書類でも行政書士が作成できる書類なら不服申立ての代理が可能になりました。
弁護士しか対応できないと考えられていた業務が行政書士でも対応できるようになったことで、申請から不服申立てまでワンストップ対応が可能になり、業務の幅が拡大しました。
4.行政書士の業務の制限規定が明確化
補助金申請に大きな影響を与える部分です。
改正により、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。」と明記されました。
第1条の3に規定する業務とは、官公署へ提出する書類の代理作成・提出を指します。
つまり、行政書士以外の人が報酬を得て申請書類を作成・提出することが明確に禁じられたのです。
行政書士と中小企業診断士の“業務の線引き”が明確化される背景
そもそも、補助金や助成金の申請書類は「官公署に提出する書類」に該当する場合が多く、書類の代理作成・申請は今回の改正前から行政書士の独占業務です。
ただ実務上は、中小企業診断士や経営コンサルタントや民間の補助金代行業者などが「書類作成支援」や「コンサルティング」の名目で関与することが広く行われてきました。
今までグレーゾーンとして認められていましたが、今回の改正で認められなくなります。
「名目を問わず報酬を受ける」ことが禁止されるため、成果報酬、コンサル料など形を変えていても、実質的に書類作成を代行していれば違法と判断されます。
今回の改正の背景には大きく3つの理由があります。まず、行政書士、中小企業診断士などの「士業」やコンサルタントとの業務の境界があいまいなため、現場で混乱を招いていました。
2つ目が闇コンサルといわれる資格を持たない人による無責任な介入です。
資格を持たない人が申請サポートを行うことで、不正申請などのトラブルが生じていました。
3つ目が電子申請やマイナポータルの普及による行政手続のデジタル化で利便性は高まったものの、煩雑さが増したことです。
今回の法改正で行政書士の業務範囲が法律で明確になったため、現場の混乱やトラブルの減少、行政書士の信頼性向上が期待できます。
中小企業診断士が対応できなくなる範囲、引き続きできる範囲
法改正より、中小企業診断士が報酬を得て書類作成・提出をすることはできなくなります。
行政に提出する書類・関連書類について無償で作成し、別途コンサル費用や顧問費用・月会費などの名目で費用をいただくことも明確に禁止されます。
なお、中小企業診断士のメインの業務である経営改善計画・事業計画の策定、補助金を活用して会社を成長させる戦略づくりは、引き続き対応できます。
今後は、事業計画、数値策定は中小企業診断士、申請書の代理作成・提出・形式確認は行政書士と、役割を分担するケースが多くなるでしょう。
補助金申請は誰に頼めばいいのか?

一括して中小企業診断士に任せられないとなると、誰に頼めばいいかわからなくなりますね。
制度上の立場・得意分野・強みが違うため、強みがある専門家に分担して依頼するのがポイントとなります。
それぞれ強みを確認してみましょう。
行政書士…申請代理の専門家
官公署に提出する書類の作成・提出代理を法律で認められている唯一の国家資格です。
書類の形式面チェック、申請代理、国や自治体の補助金の電子申請システム(jGrants等)に対応可能で、2026年1月以降、補助金申請書を行政書士以外が代理で作成・提出した場合、罰則があります。
また、建設業許可+補助金といった許認可業務との連携ができることも強みです。
中小企業診断士…経営計画策定・事業戦略サポート
日本で唯一の「経営コンサルタント系の国家資格」です。
経営戦略や事業計画、財務シミュレーションを得意とし、採択されやすい計画書を作り上げます。
多くの中小企業診断士が「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」として登録しているため、補助金の申請サポートにも強みがあります。
ものづくり補助金・事業再構築補助金などでは「認定支援機関の確認」が要件になるケースもあるほどです。
採択後の経営改善支援まで対応可能なため、中小企業にとっては優秀な伴走者といえます。
税理士、公認会計士/社会保険労務士…財務・労務データの整備サポート
税理士や公認会計士は、決算書や財務諸表の作成、数値計画の妥当性確認に強く、金融機関との連携支援や資金繰りの改善提案も可能です。
社会保険労務士は、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金など、雇用・人事・労務関連の補助金や助成金申請の際に頼れる味方です。
厚生労働省の助成金申請については、社会保険労務士が法定代理人として申請代行できる唯一の国家資格です。
・商工会・商工会議所の経営指導員
小規模事業者向け補助金に強く、申請様式の整備・サポートを強みとしています。
無料または低コストで相談できる点も魅力です。
・認定支援機関として登録している信用金庫などの金融機関
融資と補助金を組み合わせた資金計画の提案が可能です。
・民間コンサルタント(補助金コンサル)
特定分野(IT導入補助金、製造業設備投資補助金など)に特化したノウハウを持っているケースが多く、成功報酬型の契約が多い傾向です。
ただし「代理提出」は有資格者でないとできないため、コンサルタント内に有資格者がいることを確認しましょう。
経営者の立場から「誰に何を頼むのがベストか」を考えてみる
それぞれの特徴がわかったところで、誰にどの業務を頼めばいいのでしょうか。
補助金申請を行う流れとともに、具体的にみてみましょう。
情報収集、制度選定→経営者、中小企業診断士
補助金の公募要項を読み比べ、どの補助金が自社の戦略・投資内容に合うかを判断します。
戦略設計→中小企業診断士
補助金を利用して、売上拡大・業務効率化・人材育成などの戦略目標に結びつけます。
事業計画書は、社内経営企画メンバーと中小企業診断士が一緒になって考えることが大切です。
財務・収益性シミュレーション→中小企業診断士、税理士
投資費用の回収見込みや資金繰り、費用対効果の試算などは、税理士や財務に強い中小企業診断士に依頼するのがおすすめです。
書類形式要件チェック→行政書士、社会保険労務士
要件漏れを防ぐため、行政書士によるチェックが欠かせません。厚生労働省関連の補助金を利用する際は、社会保険労務士のチェックもうけましょう。補助金によっては支援機関のサポートを受けると採択率が高まります。
最終レビュー、提出→行政書士、中小企業診断士
全体のストーリーや数値の整合性、証憑準備、提出スケジュールの確認などを行います。
採択後のフォロー→中小企業診断士、行政書士
事業計画の進捗管理、設備導入などの実行管理は中小企業診断士に依頼するといいでしょう。手続きや報告書提出は行政書士に依頼します。
失敗しない専門家選びのポイント

失敗しない専門家を選ぶためのポイントを5つ紹介します。
1.過去の採択実績(件数・採択率)を確認
製造業、小売・サービス業、IT導入、雇用関連など専門家にも得意分野があります。
自社の業種にあっている専門家を選ぶことが大前提です。
得意分野があっていることを確認したら、過去の採択実績を確認しましょう。
補助金は「申請したら必ずもらえる」ものではありません。
事前の審査に加え、事業を行った後の事後の検査によって、受け取れるかが決まります。
また、補助金は原則、後払い(精算払い)です。
とくに、ものづくり補助金は年平均成長率を3.0%以上増加させるといった条件があります。
未達で事後検査に不合格だった場合、費用をかけて事業を行ったとしても補助金は受け取れず、企業が全額負担しなければなりません。
そのため、採択実績や採択率のチェックは必須です。
2.専門家を使い分ける
申請する補助金に合わせて、複数の専門家を使いわける視点も重要です。
ものづくり補助金・事業再構築補助金など、経済産業省関連の補助金を申請したい場合、中小企業診断士に計画策定を、税理士に税金面を、行政書士に書類作成・申請代理をと、分担させることが失敗しない秘訣です。
IT導入補助金なら、ITベンダーと中小企業診断士、またはITに強いコンサルタントに導入計画を依頼、申請手続きは行政書士と分担するといいでしょう。
3.「計画作成」と「申請手続き」の役割分担を理解する
経営者にとって、計画作成から申請手続きまで1人、または一つの法人に任せてしまうほうが楽です。
ただ、ここまで見てきたように2026年1月以降、申請手続きについては行政書士に依頼しないと、依頼した法人側にも罰則があります。
専門家の強みに合わせて役割を分担させたほうが申請ミスの減少、採択率の上昇につながり、効率的であることを理解しておかなければなりません。
4.成功報酬・手数料の仕組みを知っておく
成功報酬型、着手金+成功報酬型、完全固定など、報酬についてはさまざまです。
採択後に高額な報酬を請求された、成果がなくても費用だけかかったといったトラブルが多いため、契約前に必ず確認しておきましょう。
5.採択後のサポート体制があるか
補助金は申請が通った後も証憑整理、報告書作成といった実績報告が必要なほか、補助金の入金確認やその後の経営改善への活用といった対応が必要です。
補助金申請だけでなく、採択後までサポートしてくれる専門家だと安心して任せられますね。
2026年までに経営者がやっておくべきこと

2026年1月以降、行政書士法改正のため、行政書士以外が補助金申請の書類作成・提出を行うと法律違反になります。
これまで経営相談から補助金の申請まで中小企業診断士に依頼していた場合は、早急に行政書士との連携体制を作る必要があります。
中小企業診断士のネットワークから探してもらうのもいいですし、自ら相性の良い人を探すのもいいですね。
今回の法改正により、中小企業診断士には経営面のサポート、行政書士には申請の専門性が今まで以上に求められるようになります。
コンプライアンス面からも、行政書士・中小企業診断士・認定支援機関・社会保険労務士がチームを組んで取り組んだほうがいいでしょう。
また、近年のAI市場の成長に伴い、DXやAI関連の補助金が増加、より高度化していくことが予想されます。
公募されてから数ヶ月~半年程度の期限があるとはいえ、補助金申請書類の準備には時間がかかります。また、昨年あった補助金が今年もあるとは限りません。
スモールビジネス経営者としては、常に最新の補助金情報をチェックし、早めに「誰に」「いつ」相談するかが重要になるでしょう。
まとめ

2026年の制度変更はリスクではなく、よりよい体制を作るためのチャンスと捉えましょう。
専門家の強みを理解し、上手に役割分担をすることで補助金獲得の可能性が高まります。
ただ、そうはいっても日々の仕事の中で、補助金の情報を整理したり、新しい専門家をリサーチして依頼したり、申請書類を作成したりするのは大変ですね。
そんな時はスーパー秘書にお任せください。
スーパー秘書は行政書士、中小企業診断士のような専門家ではありませんが、あなたの経営をサポートします。
たとえば、あなたのビジネスに使えそうな補助金を探す、補助金の概要や申請条件・交付条件、申請スケジュールなど重要な箇所をピックアップする、新しい補助金がでたら報告するといった情報整理、あなたのビジネスにふさわしい専門家をピックアップするといったリサーチ業務に対応可能です。
また、書類作成補助など“橋渡し役”としても活躍できます。
補助金の利用を考えているけれど、何から始めたらいいかわからない、情報を整理してほしいといった内容でも構いません。お気軽にお問い合わせくださいね。