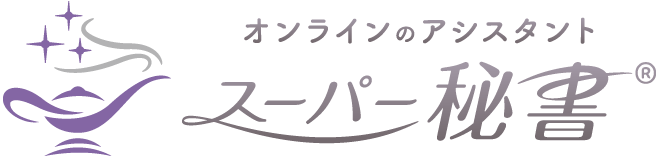2025年10月28日

2020年6月、大企業を対象に「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が施行され、2022年4月からは中小企業も含めたすべての事業主にパワハラ防止対策が義務付けられました。
そのため、業種や規模を問わず「ハラスメント」に対する意識が高まっています。
スモールビジネス経営者もすでに対策をとっているでしょう。
一方、ハラスメントを恐れるあまり、必要な指導や注意すら避けてしまうケースも増えています。
「叱ったり、強く指導したりするとパワハラと言われるかも」「本人が傷つくかもしれないから指摘しないでおこう」など、実際にやっている人も多いのではないでしょうか。
しかし、このような過剰な優しさ、配慮で部下の成長を妨げてしまうと「ホワイトハラスメント」になります。
小規模事業者の場合、人間関係が密になりやすいうえ、人手不足もあり従業員に辞めてほしくないという思いが強いため、ホワイトハラスメントが起こりやすい環境です。
ここではホワイトハラスメントの具体例や対策について紹介します。
ホワイトハラスメントとは?
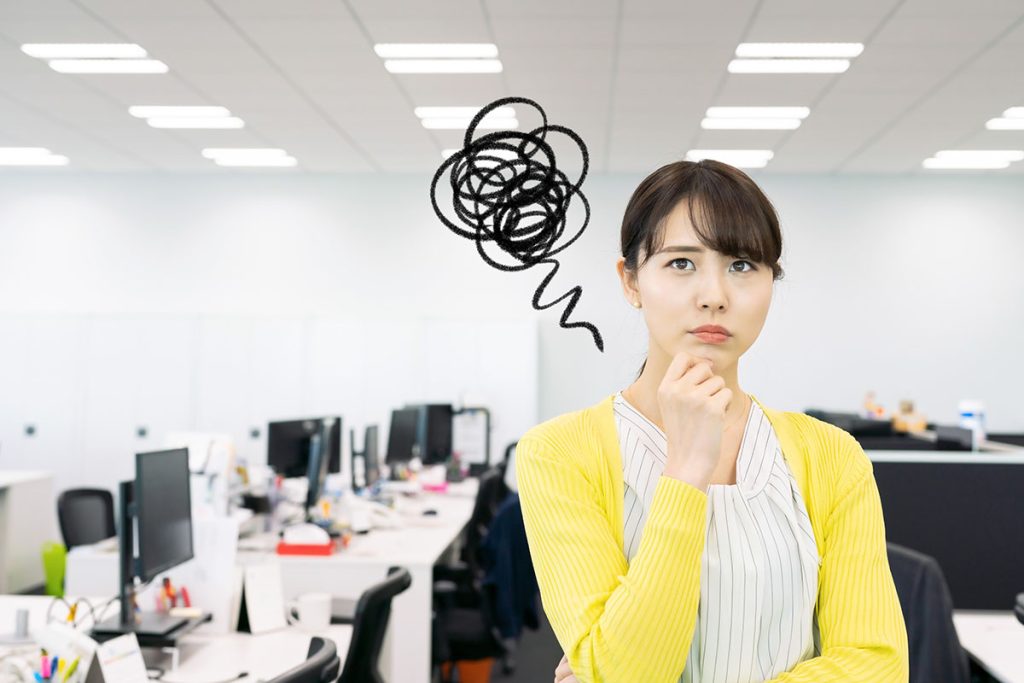
ホワイトハラスメントとは「一見、優しい言動に見えるものの、過度な配慮や強要が相手の自由や尊厳を奪う行為」を指します。
たとえば、下記のような言動はホワイトハラスメントと言えます。
適切な指導、フィードバックを行わない
「パワハラと言われるのが怖い」「傷つくかも」と配慮し、ミスがあっても改善すべき点があっても、必要な指導やフィードバックを行わない。
業務が終わらず残業になりそうだったら「あとは引き受けるよ」と上司や先輩が仕事を引き継ぐ。
難しいから、時間がかかるからと言って、詳細な業務のやり方を指導しない…。
一見、優しい対応に見えますが、ミスや改善すべき点は指導していかないと、一人のビジネスパーソンとして成長していけません。
過度な業務調整をする
家庭があるから、介護があるから、持病があるからなどを理由に、適切な量、レベルの仕事を割り振らないこともホワイトハラスメントです。
優しさから配慮したつもりでも、本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする行為はパワハラ6類型の「過小な要求」に該当します。
必要な会議やイベントに参加させない
聞いているだけで大変だからと、メンバーであっても該当会議へ出席しなくていいと言う、休日開催の会社行事は参加しなくてもいいと伝えるなどもホワイトハラスメントの一つです。
大変だろうと配慮したつもりでも、従業員や部下は、自分はこの職場で不要なのではないかと感じ、職場での孤立感が増していきます。
過度な心配をする
少し咳をしただけで「無理をしないで」と何度も声をかけたり、任せた仕事の進捗をこまめに確認したり…。
優しさからくる配慮ではありますが、度を越えるとプレッシャーになります。
社会人ですから、体調はある程度自分で管理できるでしょう。
また、自分の裁量で進めてこそ仕事にやりがいを感じるものです。
不公平な対応・評価をする
同じミスをした場合、Aさんには厳しく指導したにも関わらず、傷つきやすいBさんには指摘しない。
家庭があるCさんにはシフトを過度に配慮する。
結果が良くなくてもDさんは真面目だから高評価を付けるなど、配慮という名目で優しさが偏ると他の社員の不満が噴出し人間関係が悪化します。
ホワイトハラスメントは、配慮という名の優しさから発生しているのが特徴です。
明確な攻撃性がない分、わかりにくい面もありますが、実は当事者の尊厳を傷つけ、職場全体の士気を下げる要因になります。
小規模事業者におけるホワイトハラスメントのリスク

企業の規模を問わずホワイトハラスメントのリスクはありますが、小規模事業者のリスクは高いといえます。
主な理由は次の3点です。
人間関係の濃さ
従業員数が少ない分、個人の性格やスキル、家庭環境など、お互いに「なんとなく知っている」という状況なため、改めて聞くことを避けがちです。
その結果、過度な配慮が起こります。
距離の近さが“優しさの暴走”を招くともいえるでしょう。
人手不足
社員数が少ないと1人が複数の業務を担当しています。
人手不足の職場では、まったく余裕がないといったケースも多いでしょう。
そのため、1人辞めると仕事が回らなくなってしまいます。
経営者や上司としては、今いる社員にできる限り辞めてほしくないため、つい過剰な配慮をしてしまいがちです。
ハラスメント防止対策が不十分
法律によりハラスメント防止対策が義務付けられましたが、罰則がないため整備が進んでいない小規模事業者もあるかもしれません。
法律では、ハラスメントについて研修等を行い従業員に周知・啓発する、社内、または社外にハラスメント相談窓口を設置する、相談があった場合は迅速かつ適切に対応できる体制を整えるなどが求められています。
ホワイトハラスメントの具体例(小規模事業者編)
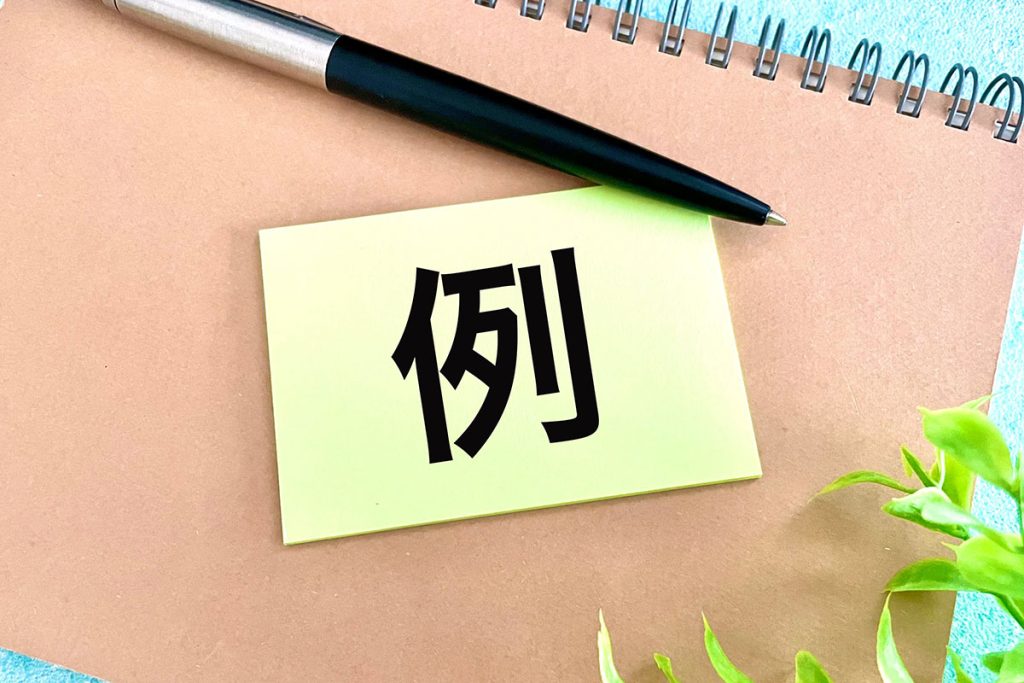
ここから小規模事業者にありがちなハラスメントの具体例、会社に与える影響について紹介します。
業務アサインの偏り→職場の雰囲気が悪化
若手や負担をかけたら辞めそうな社員、家庭がある社員には「無理しなくていい」と言って仕事量を配慮します。
しかし、会社全体の業務量は変わらないため、配慮が不要と判断された従業員に仕事が集中したり、管理職の仕事が増えたりします。
その結果、配慮された側は期待されていないと感じ、業務負担が増した側は大事にされていないと感じて、社内に不公平感が生じます。
結果として職場の雰囲気が悪化し、離職者が増加します。
配慮の押し付け→個人・企業の成長を阻害
「家庭があるから無理だよね」と勝手に判断し、適切な業務をアサインしないことは、従業員の成長の機会を逃し、キャリアアップ、収入アップを阻害します。
個人が成長しないと、企業としても成長できません。
新人教育の形骸化→新人の成長を妨害
パワハラを恐れるあまり、「厳しく指導できない」などと言って、適切に指導しないことは、新人の成長機会を奪っていることと同じです。
少し背伸びをしたら達成できるレベルの仕事に挑戦することで、ビジネスパーソンとして成長していきます。
適切なレベルの仕事の割り振り、指導が行われなければ、成長できないと感じて、新人は転職していってしまうでしょう。
その結果、再び次の新人を教育することになり、負担は増加する一方です。
“よかれ”と思っての口出し→モチベーションの低下
「この仕事は君に任せるよ」と言いながら細かく進捗を確認したり、指導したり…。
成功させてあげたいという思いがあったとしても、過度な口出しは相手にとっては負担になります。
裁量が少ないと、仕事へのモチベーションも低下しがちです。
信頼されていないと感じ、離職を検討する従業員も増えるしょう。
ホワイトハラスメントのデメリット
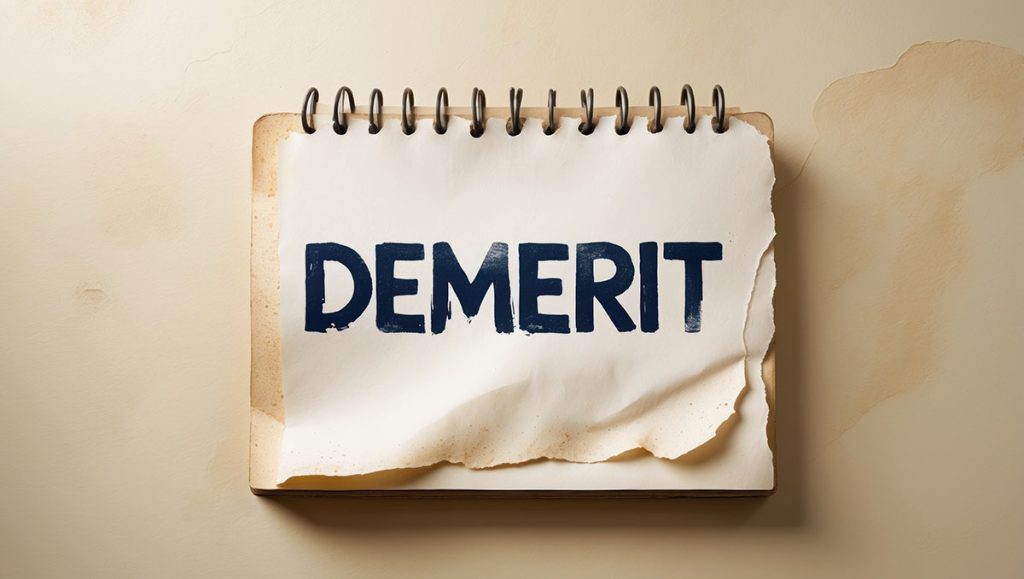
ホワイトハラスメントが発生すると、次のようなデメリットがあります。
生産性の低下
善意であっても、本人の意向を無視して仕事を減らす、能力に見合った仕事を依頼しないと、従業員は期待されていないと感じ、仕事のモチベーションが下がります。
生産性も下がるでしょう。
あの人には簡単な仕事ばかりで、私は大変な仕事ばかりと不公平感が募ると、周囲の人間のモチベーションや生産性も低下していきます。配慮された人だけでなく、周囲にも悪影響を及ぼします。
離職率の上昇
この職場では成長できない、頑張っても適正な評価を得られないと考えた従業員が離職していきます。
優秀な人材が流出することで、生産性の低下のほか、人手不足が加速することで採用・教育コストが増加します。
上司の指導力の低下
指導することを避けてしまっては、上司の指導力や育成力は伸びません。
その結果、ホワイトハラスメントが継続することになり、従業員の生産性の低下、離職率の上昇と負のスパイラルに陥ります。
上司としても、管理業務だけでなく、実務、採用、教育などさまざまな業務をすることになり、負担が増えます。
外注先との関係悪化
コア業務に集中するため、アウトソーシングを利用している経営者も多いでしょう。
外注であっても、社員同様あなたのビジネスを支えるパートナーです。
外注だからと遠慮して適切なフィードバックをしなければ、いつまでもパートナーとして成長できず、あなたは忙しいまま。
外注のメリットを活かせないまま、外注費だけがかかり続けます。
また、適切な説明もなく膨大な量の仕事を依頼するといった、まったく配慮のない対応もNGです。
外注先もより良い仕事を求めて、あなたとの関係を解消するかもしれません。
クライアントと外注先という関係上、外注先が意見を言いにくいケースも多く、過度な配慮、または配慮のなさによりビジネス関係が崩れる可能性があります。
ホワイトハラスメント防止するためにできること

では、ホワイトハラスメントを防ぐために何ができるのでしょうか。
役割と期待値を明確にする
小規模企業では、気づいた人がやる、みんなで支え合うという雰囲気が強く、誰がどこまでやるのかが不明確になりがちです。
その結果、配慮しすぎてホワイトハラスメントになったり、過度に結果を求めすぎてパワーハラスメントになったりします。
個人の業務範囲を明確にすれば、ルールで動けるようになりハラスメントが減ります。
たとえば、忙しそうにしている同僚を見た場合、何も言わずに代わりにやってあげることは優しさかもしれません。ですが、相手は望んでいない場合は仕事を奪われた、ホワイトハラスメントだと感じるかもしれません。
業務範囲が明確になっていれば、「手伝おうか?」と一声掛けることで、コミュニケーションが生まれ、ハラスメントではなくなります。
また、期待値を言語化・数値化すると、感情的な評価や誤解を防ぐことにつながります。
頑張っているから、かわいそうだからといった感情優先で評価するのではなく、事実ベースで対応できるようになります。
役割と期待値を明確にし、事実や結果に基づいて適切なフィードバックを行うことはハラスメントではありません。
小規模でもハラスメント研修を導入
ハラスメント防止対策として、ハラスメントの周知が求められています。
社内で研修できる人材がいない、社外に頼む費用が気になる場合は、無料で利用できる厚生労働省ポータルの「あかるい職場応援団」などを活用しましょう。
外注は“対等なパートナー”という意識を持つ
外注はあくまでも対等なパートナーです。
全く配慮しないのはNGですが、進捗確認や成果物のレビューを定期的に行うなど、こまめにコミュニケーションをとりましょう。
こまめにコミュニケーションをとることで、社内の情報共有が滞ることも防げます。
ホワイトハラスメント対策の課題 :結局、管理が面倒になりがち

ホワイトハラスメントについて知れば知るほど、「どこからがホワイトハラスメントになるのか」「気を遣い過ぎたかも」と迷う場面が増えるでしょう。
外注との付き合い方にも悩みますね。
結果的に、面談やミーティング、フィードバックが増えるなど管理工数が増え本業に集中できないようでは、本末転倒です。
解決策:管理に悩むなら外部に任せる選択肢も

ホワイトハラスメントに気を配りすぎて疲弊するようなら、オンラインアシスタントへの外注を検討しましょう。
感情のしがらみを減らし、ビジネスパートナーとして客観的な関係性を維持できます。
外注との関係は契約ベースのため、感情優先ではなく成果物で評価できます。
外注を利用することで、スタッフが“優しさの使い方”に悩む場面が減り、コア業務やチームワークに集中しやすくなると、社内のパワーハラスメント・ホワイトハラスメント、両方の防止につながります。
オンラインアシスタントとして定評のあるスーパー秘書では、実際に業務を行うスタッフと経営者の間にコーディネーターが入ります。複数の業務を依頼したい場合でも、コーディネーター1人に説明すれば、能力に見合ったスタッフをアサインして、仕事にあたってもらえます。複数の業務を少しずつ依頼したい小規模事業者でも安心して委託できる仕組みです。
まとめ

ホワイトハラスメントは“優しさ”が裏目に出てしまうもの。
ビジネスにおいて配慮は必要ですが、過度な配慮はハラスメントにつながります。
小規模事業者ほど人間関係が濃く、ホワイトハラスメントが起こりやすい環境のため、注意が必要です。
ハラスメントが発生した場合、適切な対応ができなければ、高額な慰謝料、賠償金の支払いを命じられることもあります。
ハラスメント防止策としては役割の明確化と事実ベース対応が肝となります。
そうはいっても実現が難しいと感じるなら、外部委託で心理的、物理的負担を減らしましょう。
スーパー秘書では、オンラインであなたのビジネスをサポートします。リサーチ、プレゼン資料作成、スケジュール管理、経理関連業務、事務局関連業務といった事務作業から、ライティングや動画作成といったクリエイティブな業務まで、コーディネーターを中心にチームを組んであなたのビジネスをサポートします。
コーディネーターは社会人経験が豊富なスタッフなため、どのような業務を依頼したらよいかわからないといった状況でも、ビジネスを整理してスーパー秘書の仕事として受けられる形に整えます。コミュニケーション力も高く、こまめにコミュニケーションをとりながら、あなたのビジネスをサポートしていきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。