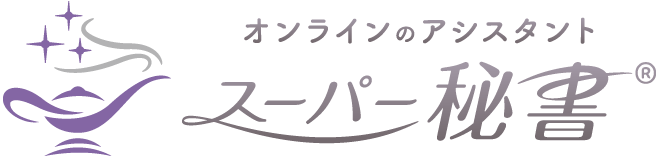2025年10月14日

経営者や担当者の方の中には、日々の細かな事務作業や調整業務に時間を取られ本来の経営判断や戦略に集中できないと感じている方も多いのではないでしょうか。
最近は、そのような課題を解決するためにオンラインアシスタントを利用する企業が増えています。
オンラインアシスタントとは、経理や資料作成、スケジュール管理などのバックオフィス業務をオンラインを通じて依頼できるサービスのことです。
複数のオンラインアシスタントを併用することで、専門分野ごとのスキルを活用しながら業務の効率化やリスク分散が可能になります。
本記事では、複数サービスを組み合わせて活用する方法や注意点を解説し、安心して導入を検討できるようにご紹介します。
複数のオンラインアシスタントを併用する経営者が増えている背景

最近、経営者や担当者が複数のオンラインアシスタントを活用する動きが目立っています。
背景には業務の複雑化や専門化、そして変化の早い市場への対応が求められる状況があります。
オンラインアシスタントは、経理や資料作成、スケジュール管理など多くの事務作業をインターネット経由で依頼できるサービスです。
1社だけに任せると、突然の人員不足や稼働停止のリスクが高くなりますが、複数サービスを組み合わせればリスク分散と業務効率化を同時に実現できます。
分野ごとの専門スキルを持つスタッフを必要に応じて柔軟に活用できることも、複数契約が選ばれる理由の一つです。
単なる外注ではなく、業務の特徴に合わせた戦略的な分担が可能な点も注目されています。
たとえば定期的に発生する事務作業は長期契約で依頼し、繁忙期の一時的な業務は短期契約で別のサービスに依頼するなど、コストと人材リソースを最適化できます。
その結果、経営者は本来の業務に集中できる時間を確保しやすくなります。
特化型サービスの登場で「選び分け」が可能に
オンラインアシスタント市場には、ここ数年で特定分野に特化したサービスが増えてきました。
つまり、企業は自社の課題に合わせて必要なサービスを選び分けることができます。
以下は主な特化型サービスの例です。
- 経理・会計支援:帳簿作成や請求書管理、税理士との連携まで対応
- マーケティング支援:SNS運用やWeb広告運用、ロングテールキーワードを意識した記事制作
- デザイン・制作:バナー作成や資料デザイン、動画編集などのクリエイティブ業務
- 営業サポート:顧客へのメール送信やアポイント調整など営業関連業務
特化型サービスを利用することで、経営者は目的ごとに適したスキルを持つスタッフを確保できます。
たとえば経理は経理特化型に、マーケティングは広告運用に強いサービスに依頼するなど、分野別に選択できます。
必要な期間だけ依頼できるスポット利用もしやすく、コストを抑えながら高い専門性を活用できる点もメリットです。
さらに多くのサービスがチャットツールやオンライン会議を活用しており、初めて利用する人でもスムーズに連携できます。
働き方の多様化とスピード感ある経営ニーズ
複数のオンラインアシスタントを活用する流れには、働き方の多様化と経営スピードの加速も関係しています。
リモートワークや副業の普及により、オンラインで専門スキルを提供する人材が増え、地域に縛られず優秀な人材を簡単にアサインできるようになりました。
一方で、ビジネス環境の変化はますます早くなり、商品企画やサービス改善に使える時間は短縮されています。
競合に先んじて施策を打つには、素早い意思決定と即応できる体制が欠かせません。
複数のオンラインアシスタントを活用することで、以下のような利点があります。
- 稼働時間の確保:複数チームを組み合わせれば、営業時間外や土日対応も可能
- 専門性の向上:それぞれの分野に強いスタッフを状況に応じて活用できる
- コスト調整の柔軟性:案件ごとに契約形態を変え、必要な時期だけ稼働時間を増減できる
オンラインアシスタントはクラウドツールやデータ共有システムを活用して遠隔地でもリアルタイムに作業を進められるため、地理的な制約がなく、急なプロジェクトにも即対応できます。
こうした柔軟な運営体制は、経営者が社内スタッフの負担を軽くしながら変化の速い市場にも対応できる安心感につながります。
複数サービスを組み合わせるメリット

複数のオンラインアシスタントを同時に活用すると、単独の契約では得にくい広がりと深さを実現できます。
特定業務に強いチームを組み合わせることで、作業の抜け漏れを減らし、突発的な変化にも強い体制を作れます。
さらに、契約時間や担当範囲を調整しやすく、コストの使い方を細かく設計できるのも魅力です。
下の表は、組み合わせ運用で得られる主な内容を、実務の観点から整理したものです。
| メリット | 内容 | 目安の運用ルール |
|---|---|---|
| 専門性の最大化 | 分野ごとに強いチームへ依頼して品質を底上げ | 業務を分類して担当を固定、レビュー用のチェックリストを共有 |
| リスク分散 | 稼働停止・人員変更・繁忙期に備える | 人材のバックアップ体制を整え、担当ごとの分担表を作成 |
| 効率と柔軟性 | 稼働量・時間帯・契約期間を細かく調整 | 月内で配分変更できるルールと成果物の定義書を先に作る |
専門性をピンポイントで活用できる
オンラインアシスタントには、経理・総務・営業サポート・制作・マーケティングなど、得意分野がはっきりしたサービスが増えています。
複数を組み合わせれば、各領域で必要なスキルを無駄なく使い分けられます。
結果としてレビュー回数が減り、社内での手戻りも抑えやすくなります。
- 経理・労務:仕訳・記帳・請求書処理・給与計算の定常業務を安定運用
→月次の締め日とチェック手順を共有しておく - 制作・デザイン:資料テンプレートやバナー、動画編集を専任化
→トンマナとNG例を事前に提示し、サンプル納品から本番納品の流れを固定 - マーケティングサポート:SNS運用やWeb広告運用、ロングテールキーワード重視のコンテンツ制作
→編集ガイドラインとタグ設計、レビューの基準を共通化させる - 営業サポート:見込み顧客リストの精査、メール配信、アポイント調整
→CRMの入力ルールと応対テンプレートを共有し、件名や差出人名の統一で反応率を安定化させる
複数運用のポイントは、依頼内容を業務カテゴリごとに分け誰がどこまで担当するかを最初に決めることです。
作業の引き継ぎはチャットとドキュメントで残し、担当交代時に迷いが出ないよう、チェックリストとサンプル成果物を共用フォルダで管理します。
万一のトラブル時にリスク分散できる
単独の契約に依存すると、担当者の離任や急な稼働停止、繁忙による遅延などが起きた際に影響が大きくなります。
複数のオンラインアシスタントを利用しておけば、バックアップや万一の運用に切り替えやすく、納期や品質を守りやすくなります。
その際、セキュリティ面では業務ごとに閲覧・編集の範囲を分け、必要最小限のアクセスに留めることが大切です。
ファイル共有はフォルダ単位で権限を切り、社内の承認なく共有範囲が広がらないようにします。
個人情報や機密情報の取り扱いは、契約書と業務マニュアルで禁止事項・保管ルール・削除期限を明記すると安心です。
業務効率化と柔軟な運用が可能
複数運用は、時間帯・繁忙期・業務に合わせて稼働を配分できるのが大きな強みです。
定常業務は毎月運用、スポット案件は短期間で一気に処理、といった使い方で全体の待ち時間を短縮できます。
社内の担当者は窓口や判断に集中できるため、手作業による業務管理の負担を軽くできます。
- 時間の効率化:早朝のレポート集計や夜間の資料整形を外部に回し、昼間は打ち合わせや意思決定に集中できる
- 繁忙期の対応:月末・四半期末などのピーク時だけ稼働を増やし、作業遅れやミスを減らすことができる
契約面では、月額固定とスポットの使い分けがポイントになります。
定常業務は固定枠で安定させ、急ぎの案件はスポットで追加発注する設計にしておくと、想定外の繁忙期にも対応できるようになります。
よくある組み合わせ事例

オンラインアシスタントを複数活用する際には、得意分野が異なるサービスを組み合わせて依頼することで業務の幅と品質を大きく広げられます。
ここでは複数サービスを組み合わせて活用する事例を紹介しながら、スーパー秘書を中心にしたメリットや運用のポイントを詳しく解説します。
特に電話対応やクリエイティブ制作、事務局業務などは日常業務の中でも負担が大きく、外部委託の効果を実感しやすい分野です。
電話代行サービス×スーパー秘書
電話対応は企業イメージや顧客満足度に直結する重要な業務ですが、社内スタッフだけで受電体制を整えるのは難しい場合があります。
そこで電話代行サービスとスーパー秘書を組み合わせると、効率的かつきめ細かい対応が可能になります。
- 案件対応速度の向上:電話代行サービスが一次受けを行い、緊急性が高い案件はスーパー秘書へ依頼することで社内リソースを節約
- 業務の優先順位付け:スーパー秘書が内容を整理し、スケジュール管理や担当者への連絡を自動化。社内の混乱を防げます
スーパー秘書は単月契約で依頼ができるため、受電のピーク時だけ依頼する柔軟な運用が可能です。
画像制作特化サービス×スーパー秘書
バナー制作や資料デザイン、SNS投稿用の画像作成など、クリエイティブ業務は専門的なスキルが求められます。
画像制作特化サービスとスーパー秘書を組み合わせると、デザインから納品までの流れをスムーズに管理できます。
- デザイン依頼の一元化:スーパー秘書が社内からの要望を整理し、画像制作サービスに正確に伝達
- スケジュール調整:納期や修正依頼をスーパー秘書が管理し、制作進行の遅延を防ぐ
- 品質チェック:完成したデザインを事前に確認し、ブランドガイドラインに沿った仕上がりをサポート
WEBマーケティング施策では、視覚的に訴求力の高いコンテンツが重要です。
スーパー秘書が依頼内容を取りまとめることで、デザイン依頼から公開までのスピードが向上し、制作チームとの連携もスムーズになります。
スーパー秘書×他のオンラインアシスタントサービス
イベントやセミナー運営、会員制サービスの事務局対応など、複数の業務を同時に進める案件では、スーパー秘書と他のオンラインアシスタントサービスを組み合わせる方法も効果的です。
- 事務局運営:他のオンラインアシスタントサービスが参加者管理やメール配信を担当し、スーパー秘書がスケジュール調整や問い合わせ対応を行うことで業務を分担
- ドキュメント整理:申し込みフォームや資料の更新をスーパー秘書が取りまとめ、社内外の情報共有を整理
- 緊急対応の安心感:突発的な変更や追加対応も、複数のオンラインアシスタントサービスを利用することで遅延なく対応可能
全国どこからでもインターネット環境があれば利用できるスーパー秘書は、遠隔地でのイベントやオンラインセミナーのバックオフィス業務にも最適です。
秘書経験やバックオフィス業務に長けたスタッフが対応するため、高品質なサポートを期待できます。
業務量や内容に応じて依頼内容を柔軟に調整できるため、短期間のプロジェクトから長期的な運営まで幅広く対応できます。
複数サービス併用の注意点

複数のオンラインアシスタントを同時に活用すると、業務の幅が広がる一方で管理の負担や情報の分散が起きやすくなります。
特に運用ルールの違い、情報共有の分散、窓口の多重化は見落としやすく気をつけたい点です。
ここでは、実務で発生しがちなリスクと、現場で使える対処方法をお伝えします。
社内の体制や業務の流れに合わせてあらかじめ枠組みを作っておくことが、ムダな手戻りやコスト超過を避ける近道になります。
| 論点 | 起きやすい状況 | 影響 | 先に決めておくと良いこと |
|---|---|---|---|
| 運用ルールの違い | 返信期限・報告頻度・成果物形式がサービスごとに違う | 期限の遅延、修正の往復、担当交代で混乱 | 共通の依頼フォーマット、評価方法、命名規則、提出手順 |
| 情報の分散 | チャット・メール・スレッドがバラバラ | 検索性の低下、最新版の取り違え | 使用ツールの一元化、検索用タグ |
| 窓口の多重化 | 担当者が複数で役割が曖昧 | ダブル発注、指示の矛盾 | 役割分担表、課題管理表 |
サービスごとに運用ルールが異なる
オンラインアシスタントごとに、対応時間、連絡の方法、成果物の形式、セキュリティ要件などが少しずつ異なります。
その差を放置すると同じ依頼でもサービスによって品質や納期がばらつき、社内の確認負担が増えます。
- 依頼テンプレート:目的・背景・完了条件・納期・優先度・参照リンク・提出形式をひとつに統一
- 評価方法:事実確認・表記ゆれ・ファイル構成・著作権・機密取り扱いの最低基準を文書化
- 成果物のルール:ファイル名の命名規則、バージョン付与、サムネイルや資料テンプレートの指定を共通化
- 時間の取り決め:返信のめやす、着手期限、リードタイムの定義と残業・土日対応の可否を明記
- セキュリティ:2段階認証、共有アカウントの禁止、閲覧権限の制限、退職・契約終了時の権限解除手順を決めておく
テンプレートを用意しておくと、新しいサービスを追加するたびにゼロから説明する必要がなくなります。
また、成果物の形式や見た目がそろうことで社内の確認が速くなります。
窓口が複数になることによる混乱
複数の外部担当者がいると、社内の誰が最終判断をするのか、誰に連絡すべきかが曖昧になりやすく、同じ依頼が二重で投げられることがあります。
矛盾する指示が出ると、納期遅延や品質低下につながります。
窓口と責任の線引きを先に決めることで、迷いを減らせます。
- 役割分担表:社内の決裁者、依頼作成者、評価担当、外部の実務担当を一覧化しておく
- 連絡の優先度:通常連絡はチャット、決裁はメール、緊急は電話など連絡経路の優先順位を定めておく
- 受付ルール:社外からの直接依頼を禁止し、必ず窓口を通す運用にしてダブル発注を防ぐ
複数サービスを束ねる役割を社内だけで担うのが難しい場合は、外部の窓口業務に任せる選択肢もあります。
依頼を受けた窓口が要件を整理し、仕様を確認したうえで制作や経理、営業サポートなどの実務に割り振る流れにすると、無駄な確認が減ります。
まとめ
複数のオンラインアシスタントを活用することで、業務の専門性を高めながらリスクを分散し、日々の作業を効率的に進めることができます。
電話対応やデザイン制作、事務局運営などを分けて依頼すれば、それぞれの分野で質の高い対応を受けられ、社内スタッフは本来の業務に集中しやすくなります。
ただしサービスごとに運用ルールが異なり、情報共有の方法や連絡窓口が複数になると混乱しやすいため、統一した依頼フォーマットや役割分担を定めることが重要です。
連絡手段や保存先をあらかじめ決めておくことで、業務全体がスムーズに流れます。
オンラインアシスタント選びに迷う方には、スーパー秘書がおすすめです。
バックオフィス業務に長けたスタッフが対応するため、質の高いサポートを安心して任せられます。
さらに全国どこからでもインターネット環境さえあれば依頼できるので、場所を選ばず利用できる利便性も魅力です。
複数サービスを組み合わせる際のサブパートナーとしても活用でき、リスク分散と効率化の同時実現において、スーパー秘書は経営者や担当者の強い味方になります。