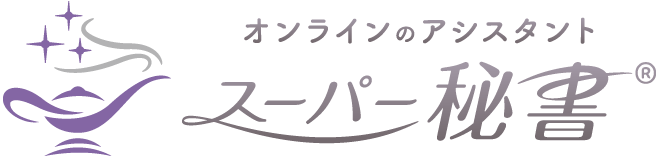2025年9月23日
2025年7月7日
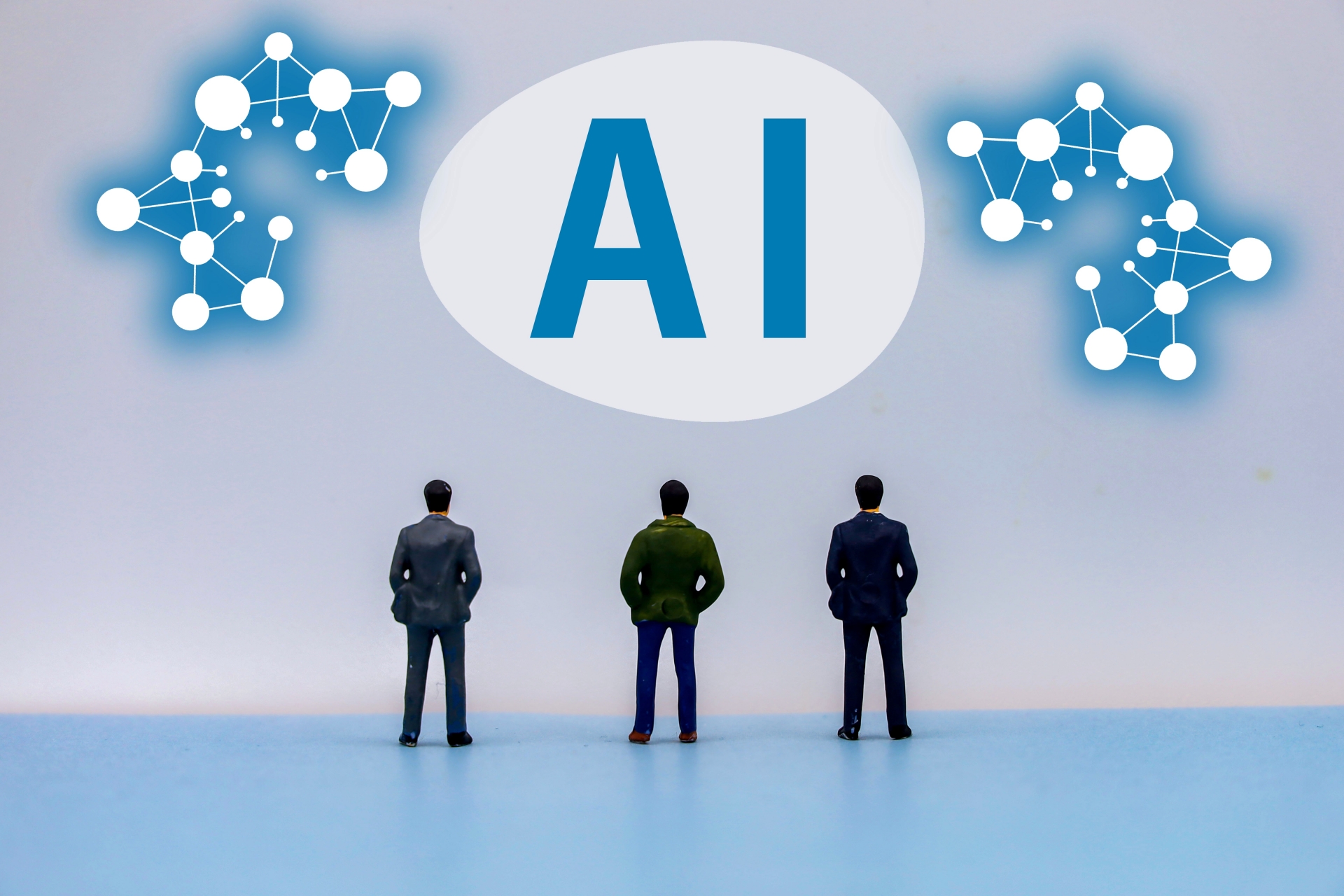
「AIを導入すれば、業務が一気に楽になると思ったのに…」
そんな声を、私たちスーパー秘書にもよくいただきます。
ChatGPTなどの生成AIが普及する中で、文章作成や資料作成などの業務は大きく変化しています。
とはいえ、AIは“使いこなせれば”便利なツールであって、「入力の工夫」や「仕上げの調整」がなければ思ったような成果が得られないのも現実です。
そこで注目されているのが、「AI × オンラインアシスタント」という組み合わせ。
私たちスーパー秘書では、AIツールを導入したい企業や、すでに使っているけれど効果を実感できていない方に向けて、日々の業務を支えるパートナーとして、AIを最大限に活かすための“準備・整理・仕上げ”まで一貫したサポートを提供しています。
この記事では、AI導入の裏側にある「人の手が必要な理由」と、それをオンラインアシスタントがどう支援できるのか、事例を交えながらご紹介します。
オンラインアシスタントとは?AI活用が進む中での役割と業務範囲を解説
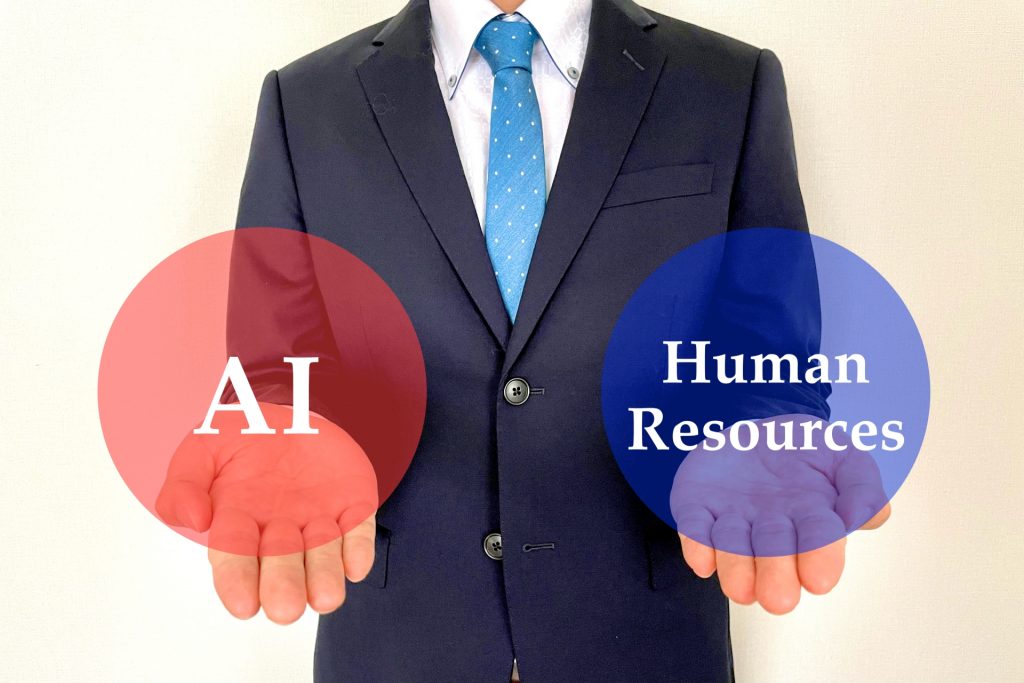
オンラインアシスタントとは何か?
オンラインアシスタントとは、インターネットを通じて業務をサポートする人材やサービスのことを指します。
従来の「秘書」や「事務スタッフ」と同じような役割を持ちつつ、場所に縛られず、在宅などのリモート環境から業務を代行してくれるのが特徴です。
特に最近では、クラウドツールやAIと連携したサポートが可能になり、企業のバックオフィス業務を効率化する手段として注目されています。
たとえば、以下のような業務がオンラインで対応されています。
- スケジュール管理:会議の設定やリマインドの送付などを代行
- 資料作成:ExcelやPowerPoint、Googleスライドなどでの資料作り
- メール対応:メールの仕分けや返信内容の下書き作成
- 経理処理:領収書の整理や請求書の作成補助
- SNS投稿補助:投稿内容の下書きやスケジュール管理
オンラインアシスタントは、専門性の高いスキルを持った人材が多いため、単純な事務作業だけでなく、マーケティング補助やWebリサーチなどの業務支援まで幅広く対応できる点が魅力です。
秘書がいない経営者のための活用術は、「秘書がいない経営者必見!オンラインアシスタントの活用術」に詳しくまとめています。
AIと組み合わせることで、何ができるの?
近年、ChatGPTや生成AIなどの普及により、AIが事務作業や文章作成を自動化するシーンが増えています。
ただし、AIに完全に業務を任せられるわけではなく、その出力内容を整える役割としてオンラインアシスタントの活用が有効です。
たとえば、以下のような使い方が広がっています。
- AIが生成した文章の文法チェックや情報補完:内容が不完全な部分を補い、読みやすく整える
- 画像や動画の簡易編集:AIで作った素材に加筆・修正を加えて納品物に仕上げる
- AI出力の要約・分類・再構成:大量に生成されたテキストを目的に応じて整理し直す
AIの導入にあたっては社内の資料や業務フローを整理する必要があるため、その準備作業もオンラインアシスタントが得意とする範囲です。
AIを使いたいけれど準備が整っていない企業にとって、オンラインアシスタントは“AI活用の第一歩”を助けてくれる存在でもあります。
中小企業や個人事業主でも使える理由
オンラインアシスタントは、大企業だけでなく中小企業や個人事業主にも導入しやすいサービスです。
その理由は次のような点にあります。
- 必要なときだけ依頼できる:フルタイムの雇用とは異なり、業務量に応じて柔軟に依頼できる
- 人材採用・教育のコストがかからない:即戦力のアシスタントが対応するため、育成が不要
- 専門スキルを持つ人に依頼できる:経理やマーケティング、資料作成など、分野ごとに経験豊富な人材を選べる
- 場所を選ばない:オフィスを持たない企業やリモート中心のチームでも活用できる
- 初期導入が簡単:特別なツールやシステムの準備がいらないサービスが多い
特に中小企業では、「人手が足りない」「雑務に時間を取られすぎている」といった悩みを抱えているケースが多くあります。
こうした状況の中、オンラインアシスタントを導入することで本業に集中できる時間が確保できるようになります。
また、クラウド型のタスク管理ツールやチャットツール(例:Slack、Chatwork、Google Chatなど)との連携がしやすいため、やり取りのハードルも低く、導入後すぐに業務を開始できるのも魅力です。
さらに、複数の業務を一括で依頼するのではなく、まずは「資料のチェックだけ」「メール整理だけ」といった小さな単位での導入が可能なので、初めてでも安心して使い始めることができます。
AI導入前の“調整業務”こそプロに任せたい!オンラインアシスタントの強みとは

AIに頼む前に「意外と面倒なこと」がある
AIは便利なツールですが、「使えばすぐに業務が終わる」というわけではありません。
AIに仕事を頼むには、目的や必要な情報を明確にして、入力するデータを整理する準備が必要です。
この準備が不十分だと、出力された内容がズレてしまったり、修正に時間がかかってしまったりします。
たとえば、「会議用の資料を作成してほしい」とAIに頼んでも、誰に向けたものか、何を伝えたいのか、どんな情報を使うのかが曖昧だと、使えない成果物が出てくることもあります。
そのため、AIに任せる前段階の“調整”こそが業務の要になるのです。
このような作業は、社内の担当者がやろうとすると本来の業務に支障が出てしまうことが多いため、オンラインアシスタントに任せると大きな負担軽減になります。
業務の整理や情報の準備はアシスタントが得意
AIに適切なアウトプットをさせるには、「インプットの質」がとても重要です。
オンラインアシスタントは、社内の情報をわかりやすくまとめたり、必要な資料やデータを整理したりするのが得意な人材です。
たとえば以下のような調整業務を任せることができます。
- 社内資料の要点をまとめる:会議資料や社内共有ファイルの内容を抜き出して整理
- 過去のやり取りを見直す:メールやチャット履歴から必要な情報を抽出
- リサーチ結果を整える:インターネットや社内データベースから集めた情報をテーマ別にまとめる
- 指示書や依頼内容を整える:AIへの指示文や依頼メモを誰が見てもわかる形に整える
情報の精度が上がることで、AIの出力結果もより使いやすくなり、修正回数が減るため、全体の作業効率が向上します。
時間がかかる資料作成もプロに任せて効率化
AIで自動的に資料を作ってもらっても、そのまま使える状態になっていることはあまり多くありません。
レイアウトの調整、不要な文言の削除、図表の配置など、“仕上げ作業”が必ず必要になります。
こうした作業は、オンラインアシスタントが得意とする分野です。
- 資料の文章チェック:文法や言葉づかいの修正、読みにくい部分の改善
- デザインの整え:フォントや色、段落などを調整して視認性を向上
- 図やグラフの追加:必要に応じて視覚的な要素を追加
- 情報の再構成:伝えたいポイントを順番や構成ごとに整理し直す
これらを自分でやろうとすると、意外と時間がかかります。
本来の業務と並行してこなすには負担が大きいため、外部の手を借りることで大きな時短になります。
オンラインアシスタントが対応可能な業務内容と活用例を紹介

どんな仕事を頼めるの?具体的な業務一覧
オンラインアシスタントには、一般的な事務作業から専門的な業務まで、幅広い業務を依頼できます。
業務の種類はサービスごとに異なりますが、多くの企業で依頼されている代表的な内容は以下のとおりです。
- スケジュール管理:会議の調整やリマインドメールの送付などをオンラインで対応
- メール対応:定型メールの下書き作成や送受信の管理
- 書類作成:社内資料・提案書・報告書などをWordやGoogleドキュメントで作成
- データ入力・管理:ExcelやGoogleスプレッドシートへの情報入力や集計業務
- Webリサーチ:市場調査や競合調査、ニュース記事の要約など
- SNS運用補助:投稿文章の作成、画像選定、スケジュール管理など
- 問い合わせ対応:チャットボットやメールでの簡易的な返答サポート
- 翻訳やライティング:英語や他言語の簡易翻訳や文章作成
このように業務範囲は柔軟で、企業の要望に合わせたカスタマイズも可能なサービスが多いです。
AIが作った文書のチェック・修正も対応可能
生成AIを使った資料作成や文章作成が普及していますが、出力された内容をそのまま使うと不自然な言い回しや誤情報が含まれていることもあります。
- 誤字脱字のチェック:読みやすさや文法を整えた校正作業
- 内容の裏取り:AIが書いた情報の事実確認や出典調査
- 表現の調整:読み手に合わせた文章のトーンや言葉の置き換え
- 見出し・構成の最適化:文章全体の流れや構成の再設計
- 用語の統一:業界用語や社内用語を使いやすく統一
こうした作業はユーザーエクスペリエンスの向上に直結するため、AIと人との連携が欠かせません。
企業別・業種別のよくある活用例
オンラインアシスタントの使い方は、企業の業種や組織規模によってさまざまです。
以下のような活用パターンがあります。
- 中小企業:人材リソースが限られているため、バックオフィス業務を中心に外注化し、経営者が本業に集中できる体制を作る
- スタートアップ:事務担当者を雇う余裕がない立ち上げ段階で、メール対応や請求業務を外部アシスタントに任せる
- EC運営企業:注文管理や商品情報の入力、レビュー対応など、日々のルーチン業務を代行
- 士業(弁護士・税理士・社労士など):顧客対応や提出書類の作成、スケジュール調整などをサポート
- 教育業界・スクール運営:入会対応や問い合わせ管理、資料発送などの事務作業を委託
- マーケティング会社:クライアントとの日程調整、資料の構成作成、SNS運用補助などを継続依頼
業務効率化を図りながら内部リソースを戦略的に振り向けられる点が、オンラインアシスタントの大きな魅力です。
業務内容が明確でなくても、「こういう作業で困っている」と相談すれば、適した担当者や業務範囲を提案してくれるため、導入のハードルも高くありません。
依頼したい業務が複数ある場合も、業務ごとに専門性のあるアシスタントが分担して対応できる体制が整っているサービスもあります。
まずは、「どの業務が時間を取っているのか」「どこから頼みたいか」を整理してみると、自社に合った活用方法が見えてきます。
オンラインアシスタントは、必要なときに必要な部分だけを支援してくれる柔軟なリソースとして、業務全体の効率を大きく変える手段となります。
オンラインアシスタントで頼める仕事の一覧は、「オンラインアシスタントの業務内容とは?依頼できる仕事をわかりやすく解説」でもご紹介しています。
AI生成物の調整はプロの手で!スーパー秘書が提供するサポート体制とは

最終調整や体裁の整えはアシスタントが丁寧に対応
オンラインアシスタントは、AIが出力した成果物を「使える形に整える」役割を果たします。
AIを使えば誰でも資料が作れると思われがちですが、実際には人の手による仕上げが成果物の品質を左右します。
以下のような調整業務を、アシスタントが丁寧に対応します。
- 表記ゆれの修正:同じ言葉でも漢字やひらがな、カタカナが混在している箇所を統一
- 用語のチェック:業界用語や社内ルールに合っているかを確認
- 文体の統一:文末表現(ですます/である)のバラつきを整える
- 体裁の調整:フォント、段落、行間、インデントなどを読みやすく整える
- スライドの視認性向上:レイアウトを整えて見やすくする
- 図表・ビジュアルの追加:文章だけでは伝わらない部分に補足素材を加える
こうした細やかな対応により、質の高い資料やコンテンツに仕上がります。
スーパー秘書のAIツール学習・勉強会の取り組み
オンラインアシスタントの中でもAIと連携して仕事を進めるには、常に最新のツールや知識に触れておく必要があります。
スーパー秘書では、日々の業務の中でAI活用に関する勉強会や情報共有の場を設け、スタッフのスキルを継続的にアップデートしています。
- 新しいAIツールの試用:ChatGPTやCanvaなど、生成系ツールを業務で試す
- 実務事例の共有:実際にどの業務でどのAIを使ったかをチームで共有
- 提案力の強化:クライアントの業務内容に合ったAIの使い方を提案するための意見交換
- セキュリティ・情報管理の理解:AIを使ううえでの注意点や機密保持の意識向上
- 社内マニュアルの整備:新しいツールやフローをすぐに取り入れられる体制づくり
こうした継続的な学習体制があることで、クライアントからの要望に柔軟かつ正確に応えられる力を持っています。
クオリティの高い成果物ができる理由
スーパー秘書では、以下のような理由から、クオリティの高い成果物を提供できています。
- ヒアリング力が高い:クライアントの要望やゴールを丁寧に汲み取って対応
- 情報整理能力に優れている:AIに投げる前の情報を的確にまとめる力がある
- 複数人によるチェック体制:必要に応じてWチェックを行い、精度を高める
- 実務経験のあるスタッフが在籍:書類作成や資料作成の経験豊富な人材が対応
- 柔軟な修正対応:納品後の修正にも柔軟に応じられる体制
オンラインアシスタントを併用することで、AIのポテンシャルを最大限に引き出し、現場で使えるアウトプットを安定的に得ることができます。
生成AIを導入して業務の効率化を考えている場合は、その仕上げを担うプロのサポートを活用することで無駄な手戻りや修正作業を大幅に削減することができます。
それが、オンラインアシスタントの強みの一つです。
まとめ
AIを使えば業務が自動で終わると思われがちですが、実際はAIに正しく働いてもらうための「準備」や「調整」がとても重要です。
その準備段階では、資料を整理したり、必要な情報をまとめたりといった作業が発生します。
このような細かいけれど欠かせない作業をスムーズに進めるためには、専門的な知識を持つオンラインアシスタントの力が役立ちます。
AIが作成した資料や文章も、そのままでは使いにくいことが多く、読みやすさや正確さを整えるために人の手で仕上げる工程が欠かせません。
スーパー秘書では、そういった仕上げ作業を丁寧に行いながら、日々AIの知識やツールについての勉強会も行っています。
そのため、AIを導入したいけれど具体的な使い方や準備方法がわからない企業にも、安心して相談できる体制が整っています。
もしAIの導入や業務の効率化に興味があるなら、最初の一歩としてぜひスーパー秘書にご相談ください。